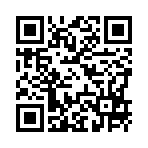2012年10月17日
『棚田ふぁむ』の棚田保全活動記(第3回)
おなじみ『棚田ふぁむ』!!
平成25年に有田川町で「全国棚田(千枚田)サミット」が開催、県としてはサミットを機に棚田保全に向けた活動を県下で展開しようと考えています。
この一環として、平成22年度に和歌山大学観光学部を中心とした皆さんに「棚田モニターツアー」を体験してもらい、結果、高齢化する地域農家だけで棚田を維持することは困難との感想を受け、棚田保全活動のボランティアを企画したところ、学生が賛同。学生によるボランティア組織『棚田ふぁむ』が結成され、平成23年度には、ソバの栽培による棚田保全活動を実施しました。
本年度も、昨年度に引き続きソバ等の栽培による棚田保全活動を計画、7月21日に有田川町沼地区の耕作放棄地において草刈活動を実施、8月26日・27日には当該箇所にソバの種を蒔きました。
今回は第3回目の活動。ソバの生育状況を確認するとともに、地元の祭りに準備段階から参加しました。
平成24年10月13日(土)~14日(日) 第3回活動
今年度、第3回目の棚田保全活動を紹介します。

活動場所は、有田郡有田川町沼地区。急傾斜でスケールが大きい棚田が素晴らしい場所で、近年ではぶどう山椒の栽培も盛んです。
しかし、高齢化等による労働力不足や耕作放棄の問題も深刻化しています。
*写真は今年度活動前の写真です。

棚田保全活動を行っている場所です。活動前の上記の写真と比較してください。前回までの草刈・ソバの播種等の作業により、ソバの花はみごと満開、黒豆も順調に育っています。
実は、前回活動から地元の方がソバを気にしてくださって、合間に点検や除草作業をしてくれていました。農作物を育てること、また農地を保全することには「まめ」な管理が必要であることを痛感します。
今回は『棚田ふぁむ』から学生7人と大浦准教授が参加。この活動で、生育状況を確認し、刈り取りを10月末~11月上旬に行うことを決めました。

ご飯を食べて、昼から地元「白山神社秋祭り」の準備。
有田川町の沼地区では毎年10月14日に白山神社で秋祭りが催されるため、前日の13日には地元の方々で祭り当日の餅まき用の餅をつきます。今年は、13日・14日が土曜日・日曜日のため、前回までの保全活動中に地元の方々と『棚田ふぁむ』との間で、「祭りに若い子が来たら盛り上がる」、「おもしろそう、参加したい」と話が盛り上がったため参加することとなりました。

13日(土)の餅つき作業です。例年2斗7升(37.8kg)のところ、今年度は若者が増えるということで、4斗8升(67.2kg)の餅米を地元が用意してくださいました。

粋な計らいで、今回は特別に「よもぎ」と「あんこ」を用意頂き、あんころ餅も作りました。餅つき作業の後、みんなで試食と交流。「やっぱり、つきたてはやわらかくておいしい」と学生達、「若い人が一緒に準備してくれて元気が出る」と地元の方々。
翌14日(日)、白山神社の秋祭り当日です。

高齢化が進んだ今となっては、神社へ餅を奉納するのに軽トラックを使って境内まで直接運んでいますが、今回は昔ながらの方法で神社へ奉納です。


公民館から神社までは、半切(はんぎり たらいの形をした底の浅い桶のこと)に餅を入れ、竹の棒で肩に担ぎます。若者の力でも、この急な地形や階段を登るのは大仕事。ましてや高齢化により、棚田の管理や伝統行事を守っていくことの大変さが身に染みて分かります。
階段を登り切ると地元からは「よう頑張った!」「こんな光景を見れるのは4,50年ぶりや」と歓声や拍手。

祭りのクライマックス、餅まきです。今回は特別に『棚田ふぁむ』から2人が餅をまく側へ参加させてもらえました。2人は「楽しかった。まんべんなく餅をまくのが難しい」との声。
今回のことで、地元の方々にも『棚田ふぁむ』を受け入れるとのことで、地元によるソバ畑の点検や奉納する際に餅を担いで通る山道や階段の草刈りや掃除など、細かい所に気を配ってくれており、『棚田ふぁむ』の元気により地元も力が湧いてきているのではないか、と感じています。
今後、10月下旬から11月上旬にソバの収穫、年度末には交流会とパワーアップしていく『棚田ふぁむ』と沼地区から目が離せません。
(文責:有田振興局農地課 宮本哲志 )
平成25年に有田川町で「全国棚田(千枚田)サミット」が開催、県としてはサミットを機に棚田保全に向けた活動を県下で展開しようと考えています。
この一環として、平成22年度に和歌山大学観光学部を中心とした皆さんに「棚田モニターツアー」を体験してもらい、結果、高齢化する地域農家だけで棚田を維持することは困難との感想を受け、棚田保全活動のボランティアを企画したところ、学生が賛同。学生によるボランティア組織『棚田ふぁむ』が結成され、平成23年度には、ソバの栽培による棚田保全活動を実施しました。
本年度も、昨年度に引き続きソバ等の栽培による棚田保全活動を計画、7月21日に有田川町沼地区の耕作放棄地において草刈活動を実施、8月26日・27日には当該箇所にソバの種を蒔きました。
今回は第3回目の活動。ソバの生育状況を確認するとともに、地元の祭りに準備段階から参加しました。
平成24年10月13日(土)~14日(日) 第3回活動
今年度、第3回目の棚田保全活動を紹介します。

活動場所は、有田郡有田川町沼地区。急傾斜でスケールが大きい棚田が素晴らしい場所で、近年ではぶどう山椒の栽培も盛んです。
しかし、高齢化等による労働力不足や耕作放棄の問題も深刻化しています。
*写真は今年度活動前の写真です。

棚田保全活動を行っている場所です。活動前の上記の写真と比較してください。前回までの草刈・ソバの播種等の作業により、ソバの花はみごと満開、黒豆も順調に育っています。
実は、前回活動から地元の方がソバを気にしてくださって、合間に点検や除草作業をしてくれていました。農作物を育てること、また農地を保全することには「まめ」な管理が必要であることを痛感します。
今回は『棚田ふぁむ』から学生7人と大浦准教授が参加。この活動で、生育状況を確認し、刈り取りを10月末~11月上旬に行うことを決めました。

ご飯を食べて、昼から地元「白山神社秋祭り」の準備。
有田川町の沼地区では毎年10月14日に白山神社で秋祭りが催されるため、前日の13日には地元の方々で祭り当日の餅まき用の餅をつきます。今年は、13日・14日が土曜日・日曜日のため、前回までの保全活動中に地元の方々と『棚田ふぁむ』との間で、「祭りに若い子が来たら盛り上がる」、「おもしろそう、参加したい」と話が盛り上がったため参加することとなりました。

13日(土)の餅つき作業です。例年2斗7升(37.8kg)のところ、今年度は若者が増えるということで、4斗8升(67.2kg)の餅米を地元が用意してくださいました。

粋な計らいで、今回は特別に「よもぎ」と「あんこ」を用意頂き、あんころ餅も作りました。餅つき作業の後、みんなで試食と交流。「やっぱり、つきたてはやわらかくておいしい」と学生達、「若い人が一緒に準備してくれて元気が出る」と地元の方々。
翌14日(日)、白山神社の秋祭り当日です。

高齢化が進んだ今となっては、神社へ餅を奉納するのに軽トラックを使って境内まで直接運んでいますが、今回は昔ながらの方法で神社へ奉納です。


公民館から神社までは、半切(はんぎり たらいの形をした底の浅い桶のこと)に餅を入れ、竹の棒で肩に担ぎます。若者の力でも、この急な地形や階段を登るのは大仕事。ましてや高齢化により、棚田の管理や伝統行事を守っていくことの大変さが身に染みて分かります。
階段を登り切ると地元からは「よう頑張った!」「こんな光景を見れるのは4,50年ぶりや」と歓声や拍手。

祭りのクライマックス、餅まきです。今回は特別に『棚田ふぁむ』から2人が餅をまく側へ参加させてもらえました。2人は「楽しかった。まんべんなく餅をまくのが難しい」との声。
今回のことで、地元の方々にも『棚田ふぁむ』を受け入れるとのことで、地元によるソバ畑の点検や奉納する際に餅を担いで通る山道や階段の草刈りや掃除など、細かい所に気を配ってくれており、『棚田ふぁむ』の元気により地元も力が湧いてきているのではないか、と感じています。
今後、10月下旬から11月上旬にソバの収穫、年度末には交流会とパワーアップしていく『棚田ふぁむ』と沼地区から目が離せません。
(文責:有田振興局農地課 宮本哲志 )
2012年10月17日
ご当地ラーメンふるさと紀行「和歌山ラーメン」プロジェクト!
食品流通課 大石です
日本の醤油の源泉は、鎌倉時代紀州の禅寺「興国寺」の開祖「法燈国師」が中国から伝えたなめ味噌(現在の金山寺味噌)がその母体とされています。このプロジェクトでは紀州徳川家の保護を受け、江戸時代には約1,000戸の町に92軒もの醤油蔵があったとされる醤油発祥の地「和歌山県湯浅町」を訪ね、豊潤な和歌山の自然を生かしつつ、昔ながらの手づくり醤油の製法を今に伝える醤油蔵で受け継がれてきた歴史や食文化を通じて“醤油のふるさとは、和歌山にあった”という歴史を今一度多くの方々に知って頂くとともに、地元に深く根を張り、ご当地ラーメンとして愛されている“和歌山ラーメン”を通じて“醤油”の魅力を再発見して頂くコラボ企画を東京の有名ラーメン店“麺や 七彩”“食堂 七彩”と食の情報誌“ラーメンWalker”とともに実施します。
プロジェクトの概要
1.醤油のふるさと 和歌山県湯浅町を訪ねて
食の情報誌「ラーメンWalker」の「ご当地ラーメンふるさと紀行【和歌山ラーメン編】誌面において“醤油のふるさと 和歌山県湯浅町”の醤油蔵で昔ながらの伝統を現代に伝える職人の手仕事や技を特集します。
(角川マガジンズ発刊 ラーメンWalker2013東京23区版 平成24年10月18日発売)
2.東京の有名ラーメン店“麺や 七彩”“食堂 七彩”で和歌山ラーメンが発売!
化学調味料を使用しない「無化調ラーメン」で知られる“食堂七彩”の店主・阪田博昭氏。素材を知り尽くした阪田氏が、究極の醤油ラーメンを作るべく醤油発祥の地湯浅町を訪れ、そこで出会ったのが、天保12年創業以来170年江戸時代から変わらない醤油づくりに取り組んできた醤油蔵「角長」。老舗の醤油蔵で醸し出された手作り醤油を使った「古くて新しい誰も食べたことがない和歌山ラーメン」が東京駅ラーメンストリート内「麺や 七彩」、中野区鷺宮の「食堂 七彩」の2店舗で10月18日から限定発売されます。首都圏の皆様はもちろんのこと、和歌山県の方も東京にお出かけの際は是非お試し下さい!


日本の醤油の源泉は、鎌倉時代紀州の禅寺「興国寺」の開祖「法燈国師」が中国から伝えたなめ味噌(現在の金山寺味噌)がその母体とされています。このプロジェクトでは紀州徳川家の保護を受け、江戸時代には約1,000戸の町に92軒もの醤油蔵があったとされる醤油発祥の地「和歌山県湯浅町」を訪ね、豊潤な和歌山の自然を生かしつつ、昔ながらの手づくり醤油の製法を今に伝える醤油蔵で受け継がれてきた歴史や食文化を通じて“醤油のふるさとは、和歌山にあった”という歴史を今一度多くの方々に知って頂くとともに、地元に深く根を張り、ご当地ラーメンとして愛されている“和歌山ラーメン”を通じて“醤油”の魅力を再発見して頂くコラボ企画を東京の有名ラーメン店“麺や 七彩”“食堂 七彩”と食の情報誌“ラーメンWalker”とともに実施します。
プロジェクトの概要
1.醤油のふるさと 和歌山県湯浅町を訪ねて
食の情報誌「ラーメンWalker」の「ご当地ラーメンふるさと紀行【和歌山ラーメン編】誌面において“醤油のふるさと 和歌山県湯浅町”の醤油蔵で昔ながらの伝統を現代に伝える職人の手仕事や技を特集します。
(角川マガジンズ発刊 ラーメンWalker2013東京23区版 平成24年10月18日発売)
2.東京の有名ラーメン店“麺や 七彩”“食堂 七彩”で和歌山ラーメンが発売!
化学調味料を使用しない「無化調ラーメン」で知られる“食堂七彩”の店主・阪田博昭氏。素材を知り尽くした阪田氏が、究極の醤油ラーメンを作るべく醤油発祥の地湯浅町を訪れ、そこで出会ったのが、天保12年創業以来170年江戸時代から変わらない醤油づくりに取り組んできた醤油蔵「角長」。老舗の醤油蔵で醸し出された手作り醤油を使った「古くて新しい誰も食べたことがない和歌山ラーメン」が東京駅ラーメンストリート内「麺や 七彩」、中野区鷺宮の「食堂 七彩」の2店舗で10月18日から限定発売されます。首都圏の皆様はもちろんのこと、和歌山県の方も東京にお出かけの際は是非お試し下さい!


2012年10月17日
「和歌山県レッドデータブック」2012年改訂版公表!
和歌山県では、絶滅のおそれのある生物の状況などを記した「和歌山県レッドデータブック」を平成13年(2001年)3月に発刊していましたが、その後の野生生物の育成・生息環境の変化や、自然環境についての研究成果などを踏まえて、新たに「和歌山県レッドデータブック-2012年改訂版」を公表しました。
大きさはほぼ職業別電話帳と同じぐらいで、結構ボリュームがあります。
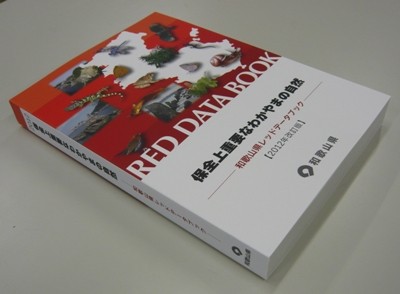
2001年版と2012年改訂版を比較すると、掲載動植物数は857種から974種となり13.7%増加しているそうです。
中には絶滅したと考えられていた種で新たに生息地が発見されたカワネジガイのようなものもありますが、総じて生育環境の悪化などによりランクインしているものが多いようです。その中には、ニホンリス、ニホンイモリ、ドジョウ、クツワムシ、ハンミョウといったよく知っている動物が入っているとのことで、知らない間に減少していることに、少し驚きました。

この「レッドデータブック2012年改訂版」は、和歌山県庁情報公開コーナーで1冊3,000円で販売中です。
また、電子データは和歌山県庁自然環境室ホームページで昨日(10/16)から閲覧可能(PDFファイル)となっています。こちらはもちろん無料です。
和歌山の自然を見直すきっかけになると思いますので、一度ご覧になってください。
(文責:広報課 林 清仁) 続きを読む
大きさはほぼ職業別電話帳と同じぐらいで、結構ボリュームがあります。
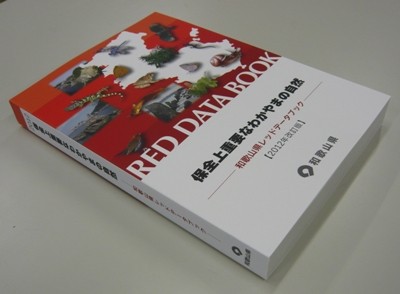
2001年版と2012年改訂版を比較すると、掲載動植物数は857種から974種となり13.7%増加しているそうです。
中には絶滅したと考えられていた種で新たに生息地が発見されたカワネジガイのようなものもありますが、総じて生育環境の悪化などによりランクインしているものが多いようです。その中には、ニホンリス、ニホンイモリ、ドジョウ、クツワムシ、ハンミョウといったよく知っている動物が入っているとのことで、知らない間に減少していることに、少し驚きました。

この「レッドデータブック2012年改訂版」は、和歌山県庁情報公開コーナーで1冊3,000円で販売中です。
また、電子データは和歌山県庁自然環境室ホームページで昨日(10/16)から閲覧可能(PDFファイル)となっています。こちらはもちろん無料です。
和歌山の自然を見直すきっかけになると思いますので、一度ご覧になってください。
(文責:広報課 林 清仁) 続きを読む
2012年10月17日
子育て支援者向け研修事業でウインズ平阪さん熱唱【水産試験場】
東牟婁振興局が事務局を務める東牟婁地方地域活動連絡協議会の子育て支援者向け研修会が、10月14日(日)に串本町の和歌山県水産試験場で開催されました。
この研修会は、財団法人 こども未来財団の補助を受けて3年前から実施しているものです。
平成22年度にはファザーリングジャパン代表の安藤哲也さんによる男性の子育て支援講座やWANA関西代表の藤木美奈子さんによる児童虐待防止の講演、平成23年度にはサカモトキッチンスタジオ主宰の坂本廣子さんによる災害時の調理法についての講義など、豪華講師陣による充実した研修を行ってきました。
そして今年度は、和歌山県出身のシンガーソングライター、ウインズ平阪さんを講師に迎え、食育についてのお話しをしていただくことになりました。
まず、東牟婁地方地域活動連絡協議会事務局から事業報告があり、続いて各市町の地域活動連絡協議会から声かけ運動や子ども神輿、ジュニアリーダー研修などの取り組み状況について報告がありました。

その後、いよいよウインズ平阪さんによる講演が始まりました。

平阪さんのご実家はお米屋さんを営んでいるとのことで、食育についてのお話しから始まり、軽妙なトークで参加者の笑いを誘っていました。

また、親が子どもに向かって「こんなとこ(和歌山)にいつまでもおったらアカンで!」などとて言うのは絶対にダメで、和歌山を誇りに思い、和歌山で活躍する大人に育てていかなくてはなりません、と熱く語っていました。
さて、講演が終わると、2015年紀の国わかやま国体のマスコットキャラクター、きいちゃんが登場しました

そしてウインズ平阪さんと、ウインズの女性ボーカルである宮本恵梨菜さんが、紀の国わかやま国体のイメージソング、「明日へと」を熱唱してくれました
この曲は、ウインズ平阪さんが作詞・作曲したもので、まるでオリンピックのテーマソングのような元気の出る曲なんです。
オリジナルバージョンを宮本さんが歌い、ダンスバージョンをウインズ平阪さんが歌ってくれました。

この「明日へと」の他にも何曲か歌っていただき、ウインズ平阪さんの絶妙なリードにより会場はとても盛り上がっていました。

講演終了後、会場の隅に用意されていた和歌山県産品の試食コーナーでは、参加者の皆さんが、梅干しや金山寺味噌、そして串本町のキンカンジャムなどの県内産品に舌鼓を打っていました。

この後、和歌山県水産試験場の見学会が行われ、向野研究員が現在取り組んでいる研究内容について解説してくれました。

ナマコの養殖にも取り組んでいるとのことで、皆さん恐る恐るナマコに触れていました

今回の研修会は非常に盛りだくさんの内容で、参加者の皆さんはとても満足していただいたようでした
さて、ウインズ平阪さんと宮本恵梨菜さんは、10月15日(月)に新宮市で行われたwbs和歌山放送のラジオフェスティバルにもご参加いただき、紀の国わかやま国体イメージソングを披露していただきました。

写真左がウインズ平阪さん、中央は新宮市熊野川町出身のシンガーソングライター・丸石輝正さん、右が宮本恵梨菜さんです。
2015年紀の国わかやま国体イメージソング「明日へと」は、これから耳にする機会がどんどん増えてくると思います。
3年後の開催に向けて、みんなで盛り上げていきましょう
【参考URL】
◆財団法人 こども未来財団
http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/
◆2015年紀の国わかやま国体・大会
http://www.wakayama2015.jp/
◆ウインズ公式サイト
http://winds-wakayama.com/
◆ウインズ公式ブログ
http://winds.ikora.tv/
◆丸石輝正 公式サイト
http://www.maruteru.jp/
【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】
この研修会は、財団法人 こども未来財団の補助を受けて3年前から実施しているものです。
平成22年度にはファザーリングジャパン代表の安藤哲也さんによる男性の子育て支援講座やWANA関西代表の藤木美奈子さんによる児童虐待防止の講演、平成23年度にはサカモトキッチンスタジオ主宰の坂本廣子さんによる災害時の調理法についての講義など、豪華講師陣による充実した研修を行ってきました。
そして今年度は、和歌山県出身のシンガーソングライター、ウインズ平阪さんを講師に迎え、食育についてのお話しをしていただくことになりました。
まず、東牟婁地方地域活動連絡協議会事務局から事業報告があり、続いて各市町の地域活動連絡協議会から声かけ運動や子ども神輿、ジュニアリーダー研修などの取り組み状況について報告がありました。

その後、いよいよウインズ平阪さんによる講演が始まりました。

平阪さんのご実家はお米屋さんを営んでいるとのことで、食育についてのお話しから始まり、軽妙なトークで参加者の笑いを誘っていました。

また、親が子どもに向かって「こんなとこ(和歌山)にいつまでもおったらアカンで!」などとて言うのは絶対にダメで、和歌山を誇りに思い、和歌山で活躍する大人に育てていかなくてはなりません、と熱く語っていました。
さて、講演が終わると、2015年紀の国わかやま国体のマスコットキャラクター、きいちゃんが登場しました


そしてウインズ平阪さんと、ウインズの女性ボーカルである宮本恵梨菜さんが、紀の国わかやま国体のイメージソング、「明日へと」を熱唱してくれました

この曲は、ウインズ平阪さんが作詞・作曲したもので、まるでオリンピックのテーマソングのような元気の出る曲なんです。
オリジナルバージョンを宮本さんが歌い、ダンスバージョンをウインズ平阪さんが歌ってくれました。

この「明日へと」の他にも何曲か歌っていただき、ウインズ平阪さんの絶妙なリードにより会場はとても盛り上がっていました。

講演終了後、会場の隅に用意されていた和歌山県産品の試食コーナーでは、参加者の皆さんが、梅干しや金山寺味噌、そして串本町のキンカンジャムなどの県内産品に舌鼓を打っていました。

この後、和歌山県水産試験場の見学会が行われ、向野研究員が現在取り組んでいる研究内容について解説してくれました。

ナマコの養殖にも取り組んでいるとのことで、皆さん恐る恐るナマコに触れていました


今回の研修会は非常に盛りだくさんの内容で、参加者の皆さんはとても満足していただいたようでした

さて、ウインズ平阪さんと宮本恵梨菜さんは、10月15日(月)に新宮市で行われたwbs和歌山放送のラジオフェスティバルにもご参加いただき、紀の国わかやま国体イメージソングを披露していただきました。

写真左がウインズ平阪さん、中央は新宮市熊野川町出身のシンガーソングライター・丸石輝正さん、右が宮本恵梨菜さんです。
2015年紀の国わかやま国体イメージソング「明日へと」は、これから耳にする機会がどんどん増えてくると思います。
3年後の開催に向けて、みんなで盛り上げていきましょう

【参考URL】
◆財団法人 こども未来財団
http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/
◆2015年紀の国わかやま国体・大会
http://www.wakayama2015.jp/
◆ウインズ公式サイト
http://winds-wakayama.com/
◆ウインズ公式ブログ
http://winds.ikora.tv/
◆丸石輝正 公式サイト
http://www.maruteru.jp/
【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】