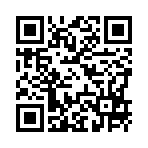2013年06月21日
6/21柿・紀の川梅干を使った料理講習会を開催
平成25年6月21日、高野山観光協会にて、地域食材である柿・紀の川梅干を使った料理講習会を開催しました
この講習会は、和歌山県紀北地方の柿と梅の地産地消を推進するため、伊都振興局・那賀振興局の主催で開催しました。
和歌山県は柿の生産量が全国1位で、そのうち伊都・那賀地方を合わせて県下の92%を占め、あんぽ柿等年間を通じて使える柿加工品もあります。伊都振興局では、柿を料理に活用することを推進しています。
また、梅干は県を代表する加工食品ですが、流通のほとんどが調味梅干となっているので、那賀振興局では、木熟梅を塩と砂糖で漬けた昔ながらのしょっぱさと酸っぱさを持ちながらまろやかに仕上げた紀の川梅干の加工方法の普及を行っています。
さて、講習会の様子です。
柿、梅について特徴、生産状況や品種等を説明したあと、紀の川梅干の漬け方について実演がなされました。
塩と砂糖を入れて漬けていきます。

次に柿料理・梅料理の説明をしたあと、試食をしていただきました。
豆乳寒天の柿ソース添え、柿ようかん、柿の粕漬け、かぼちゃの梅煮、髙野豆腐の梅あんかけなどに参加者のみなさまは舌鼓を打っていました。


高野山の宿坊で、観光客の方々に、和歌山県を代表する特産品の柿・梅干を提供することができれば、旅行先でのおもてなしとして、その地方ならではの食材を期待する気持ちに応えることができるはずです。また、和歌山県のPRや新しい食べ方を紹介する機会となります。
興味を持たれたみなさまも、柿料理や梅料理、梅干しづくりにチャレンジしてみてください
柿を使ったアイデア料理(伊都振興局ホームページ)
文責 伊都振興局企画産業課 鍵本 典子

この講習会は、和歌山県紀北地方の柿と梅の地産地消を推進するため、伊都振興局・那賀振興局の主催で開催しました。
和歌山県は柿の生産量が全国1位で、そのうち伊都・那賀地方を合わせて県下の92%を占め、あんぽ柿等年間を通じて使える柿加工品もあります。伊都振興局では、柿を料理に活用することを推進しています。
また、梅干は県を代表する加工食品ですが、流通のほとんどが調味梅干となっているので、那賀振興局では、木熟梅を塩と砂糖で漬けた昔ながらのしょっぱさと酸っぱさを持ちながらまろやかに仕上げた紀の川梅干の加工方法の普及を行っています。
さて、講習会の様子です。
柿、梅について特徴、生産状況や品種等を説明したあと、紀の川梅干の漬け方について実演がなされました。
塩と砂糖を入れて漬けていきます。

次に柿料理・梅料理の説明をしたあと、試食をしていただきました。
豆乳寒天の柿ソース添え、柿ようかん、柿の粕漬け、かぼちゃの梅煮、髙野豆腐の梅あんかけなどに参加者のみなさまは舌鼓を打っていました。


高野山の宿坊で、観光客の方々に、和歌山県を代表する特産品の柿・梅干を提供することができれば、旅行先でのおもてなしとして、その地方ならではの食材を期待する気持ちに応えることができるはずです。また、和歌山県のPRや新しい食べ方を紹介する機会となります。
興味を持たれたみなさまも、柿料理や梅料理、梅干しづくりにチャレンジしてみてください

柿を使ったアイデア料理(伊都振興局ホームページ)
文責 伊都振興局企画産業課 鍵本 典子
2013年06月21日
ミカンが二次落果を迎えています
果樹試験場です。
以前(5月29日)に「ミカンの生理落果がピークです」とこのブログで報告しました。
その時期の生理落果を一次落果、今の時期の生理落果を二次落果といいます。以前にも書きましたが、一次落果と二次落果で落果の仕方が違います。写真を見比べてください。
一次落果で落ちた果実(5月28日)。

二次落果で落ちた果実(6月20日)。

お気づきでしょうか?1ヶ月近く経っているので果実が大きくなっているのはもちろんですが、落ち方が大きく違っています。一次落果では果実とへたがくっついたまま軸(果梗(かこう)といいます)ごと落ちるのですが、二次落果ではへたを樹に残したまま、果実だけが落ちます。
樹と花・果実の結びつきは生育が進むほど強くなります。果実の小さいときは果梗がうまくつながっていないため果梗ごと落ちますが、大きくなって果梗がきちんとつながっていても果実とうまくつながっていない場合には果実だけが落ちます。そして全てがうまくつながった果実は最後まで樹に残ります。
7月以降になると生理落果も落ち着き、樹に残った果実の中から味や外観の悪い果実を人の手で落とす「摘果(てきか)」という作業が始まります。
炎天下でのつらい作業になりますが、消費者の皆さんにおいしいミカンを届けるために手を抜けない作業です。
ちなみに生理落果の調査結果は果樹試験場のホームページ(http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070109/gaiyou/002/002.htm)で公開しています。
(文責 果樹試験場 中谷 章)
以前(5月29日)に「ミカンの生理落果がピークです」とこのブログで報告しました。
その時期の生理落果を一次落果、今の時期の生理落果を二次落果といいます。以前にも書きましたが、一次落果と二次落果で落果の仕方が違います。写真を見比べてください。
一次落果で落ちた果実(5月28日)。

二次落果で落ちた果実(6月20日)。

お気づきでしょうか?1ヶ月近く経っているので果実が大きくなっているのはもちろんですが、落ち方が大きく違っています。一次落果では果実とへたがくっついたまま軸(果梗(かこう)といいます)ごと落ちるのですが、二次落果ではへたを樹に残したまま、果実だけが落ちます。
樹と花・果実の結びつきは生育が進むほど強くなります。果実の小さいときは果梗がうまくつながっていないため果梗ごと落ちますが、大きくなって果梗がきちんとつながっていても果実とうまくつながっていない場合には果実だけが落ちます。そして全てがうまくつながった果実は最後まで樹に残ります。
7月以降になると生理落果も落ち着き、樹に残った果実の中から味や外観の悪い果実を人の手で落とす「摘果(てきか)」という作業が始まります。
炎天下でのつらい作業になりますが、消費者の皆さんにおいしいミカンを届けるために手を抜けない作業です。
ちなみに生理落果の調査結果は果樹試験場のホームページ(http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070109/gaiyou/002/002.htm)で公開しています。
(文責 果樹試験場 中谷 章)
2013年06月21日
BSスカパー!「釣りビジョン」で有田川の鮎釣りを紹介
有田振興局企画産業課です。
スカパー!BS251chで、「Thanks for the earth~地球に感謝」をコンセプトに、釣りを中心としたアウトドア番組を放送しているチャンネル「釣りビジョン」。このチャンネルで、有田川の鮎釣りを紹介してくれます。
取材していただいたのは、「釣りビジョン」内で、鮎釣りの名手達が持てる技術・知識を基にシーズン毎の釣りを紐解いていく「鮎2013」という番組です。収録は、6月6日から7日にかけて有田川町で行われました。

今回登場する鮎釣り名人は、有田川をホームグランドにしている上西啓文さんです。有田川の鮎釣りや、上西さんの釣りテクニックなどを紹介しながら、収録が行われました。番組では、有田川の美しい景色と、そこに生きる美しい鮎が映し出されますので、釣りファンはもちろん、釣りファンでなくても楽しめそうです。
放送は、スカパー!BS251ch「釣りビジョン」で、6月24日(月)から放送されます。放送日により放送時間が異なりますので、番組のホームページでご確認下さい。

有田川は、全国に先駆けて5月1日に鮎釣りが解禁されています。有田川の鮎は、その姿も美しいのですが、おいしさも格別です。今シーズンは是非、有田川の鮎釣りを楽しんでみて下さい。
なお、有田川の鮎釣りについてのお問い合わせは有田川漁業協同組合まで。
(文責:有田振興局企画産業課 児嶋史晃)
スカパー!BS251chで、「Thanks for the earth~地球に感謝」をコンセプトに、釣りを中心としたアウトドア番組を放送しているチャンネル「釣りビジョン」。このチャンネルで、有田川の鮎釣りを紹介してくれます。
取材していただいたのは、「釣りビジョン」内で、鮎釣りの名手達が持てる技術・知識を基にシーズン毎の釣りを紐解いていく「鮎2013」という番組です。収録は、6月6日から7日にかけて有田川町で行われました。

今回登場する鮎釣り名人は、有田川をホームグランドにしている上西啓文さんです。有田川の鮎釣りや、上西さんの釣りテクニックなどを紹介しながら、収録が行われました。番組では、有田川の美しい景色と、そこに生きる美しい鮎が映し出されますので、釣りファンはもちろん、釣りファンでなくても楽しめそうです。
放送は、スカパー!BS251ch「釣りビジョン」で、6月24日(月)から放送されます。放送日により放送時間が異なりますので、番組のホームページでご確認下さい。

有田川は、全国に先駆けて5月1日に鮎釣りが解禁されています。有田川の鮎は、その姿も美しいのですが、おいしさも格別です。今シーズンは是非、有田川の鮎釣りを楽しんでみて下さい。
なお、有田川の鮎釣りについてのお問い合わせは有田川漁業協同組合まで。
(文責:有田振興局企画産業課 児嶋史晃)
2013年06月21日
【農業大学校】高島屋和歌山店にて出張和農市開催!
農業大学校では、毎週木曜日、校内において「和農市」という直売所を開催しています。
また、年に数回、校内だけでなく、校外でも和農市を開催してきました。

↑昨年、美園商店街(和歌山市)で開催した出張和農市
この度、開店40周年を迎えた高島屋和歌山店とコラボし、明日6月22日(土)、7月13日(土)、8月24日(土)の3回、高島屋和歌山店にて和農市を開催することになりました。詳細はこちら。
皆様、ぜひお越し下さい。
農業大学校では、農産物を作るだけでなく、消費者に販売することにも力を入れています。
学生には、和農市を通じて、「もうかる農業」「生産者の顔が見える農業」を勉強してもらいたいと思います。
<文責:農業大学校 南方高志>
また、年に数回、校内だけでなく、校外でも和農市を開催してきました。

↑昨年、美園商店街(和歌山市)で開催した出張和農市
この度、開店40周年を迎えた高島屋和歌山店とコラボし、明日6月22日(土)、7月13日(土)、8月24日(土)の3回、高島屋和歌山店にて和農市を開催することになりました。詳細はこちら。
皆様、ぜひお越し下さい。
農業大学校では、農産物を作るだけでなく、消費者に販売することにも力を入れています。
学生には、和農市を通じて、「もうかる農業」「生産者の顔が見える農業」を勉強してもらいたいと思います。
<文責:農業大学校 南方高志>
2013年06月21日
信州大学・巡検(潮岬・橋杭岩・大狗子半島)
信州大学の皆さん(教員・学生 約30人)が、6月15日、16日に紀伊半島の巡検(調査旅行)におとずれました。学生の皆さんは原山 教授と山田 准教授による解説を聞きながら、本物の地層を見学することで紀伊半島の地質への理解を深めました。
紀南では南紀熊野ジオパーク構想地域の中のすさみ町、串本町、那智勝浦町のジオサイト(候補地)での観察が行われました。(すさみ町のフェニックス褶曲は、西牟婁振興局の濱岡さんがリポートされています。)
6月15日
(フェニックス褶曲)
こちらをご覧ください。(濱岡さんのリポート)
→ http://wakayamapr.ikora.tv/e916922.html
(潮岬)
潮岬灯台を過ぎて、潮御埼神社の横の坂道を降りると海岸に出ます。ここでは、かつての海底で作られた枕状溶岩を観察することができました。また、そこに割り込んだマグマからできた岩石(グラノファイアー、ドレライト、玄武岩など)も見られました。

(橋杭岩)
道の駅の駐車場から橋杭岩の海岸を歩き、橋杭岩や海岸の転石を観察しました。ここでは、橋杭岩が熊野層群に割り込んだ境目が観察できました。学生の間からは、実物の橋杭岩を前にして、「おー、すごい。」「やっぱり、本物はいい。」との声が上がっていました。

6月16日
(大狗子半島)
那智勝浦町狗子ノ川の国道の旧道から山沿いの道をとおって海岸に下りました。ここでは、南紀熊野ジオパーク推進協議会学術専門委員の後さんの協力を得て、磯に広がる熊野酸性岩の岩石の変化を観察しました。

このあと、信州大学の皆さんは長野県の松本市まで戻られました。
*地層観察などの野外活動は、ヘルメットや手袋を着用したり、周囲の状況を確認したりするなど安全に気をつけて行ってください。
(文責:和歌山県自然環境室 田原敬治)
紀南では南紀熊野ジオパーク構想地域の中のすさみ町、串本町、那智勝浦町のジオサイト(候補地)での観察が行われました。(すさみ町のフェニックス褶曲は、西牟婁振興局の濱岡さんがリポートされています。)
6月15日
(フェニックス褶曲)
こちらをご覧ください。(濱岡さんのリポート)
→ http://wakayamapr.ikora.tv/e916922.html
(潮岬)
潮岬灯台を過ぎて、潮御埼神社の横の坂道を降りると海岸に出ます。ここでは、かつての海底で作られた枕状溶岩を観察することができました。また、そこに割り込んだマグマからできた岩石(グラノファイアー、ドレライト、玄武岩など)も見られました。

(橋杭岩)
道の駅の駐車場から橋杭岩の海岸を歩き、橋杭岩や海岸の転石を観察しました。ここでは、橋杭岩が熊野層群に割り込んだ境目が観察できました。学生の間からは、実物の橋杭岩を前にして、「おー、すごい。」「やっぱり、本物はいい。」との声が上がっていました。

6月16日
(大狗子半島)
那智勝浦町狗子ノ川の国道の旧道から山沿いの道をとおって海岸に下りました。ここでは、南紀熊野ジオパーク推進協議会学術専門委員の後さんの協力を得て、磯に広がる熊野酸性岩の岩石の変化を観察しました。

このあと、信州大学の皆さんは長野県の松本市まで戻られました。
*地層観察などの野外活動は、ヘルメットや手袋を着用したり、周囲の状況を確認したりするなど安全に気をつけて行ってください。
(文責:和歌山県自然環境室 田原敬治)