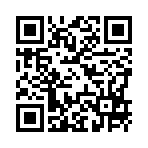2013年01月30日
和大学生サークル「アグリコ」が自治体等と農村活性化協定締結!
アグリコ(agrico.)は、和歌山大学学生によるサークルで、部員は現在29名です。中山間地域の農業支援のみならず、地域活性化のため地区のお祭りや農業体験イベントのサポーターとして、県内各地で活動を行っています。
当課では平成20年度から、県内大学生の行動力やアイデアを活用し、援農を基本とした継続的な中山間地域の支援体制構築に向け、地域との関係づくりや学生による地域支援活動等を行うシステムモデルの構築を目指すため、学生参画地域づくり体制サポートモデル事業を (財)和歌山社会経済研究所に委託しています。
(財)和歌山社会経済研究所は、平成20年度に和歌山大学経済学部ゼミの学生を中心に、学生の意識調査、受入地との意見交換を行いました。これがきっかけで農村の課題に気づいた学生が継続して援農活動に参加し、平成21年度に活性化のための組織化に向けた意識が芽生えました。
平成22年度には農業・農村交流サークル「アグリコ」を結成。平成23年度に和歌山大学から正式にサークルとして承認されました。
このたび、アグリコと受入地が、元気な地域づくりを目指して協定を締結することになりました。
締結先は、有田川町の沼谷区、紀の川市の林ヶ峯地区にある林ケ峯農産加工グループ「長寿の郷」、紀の里農業協同組合体験農業部会です。1月30日(水)午前10時30分から有田川町長、午後3時30分から紀の川市副市長立ち会いのもと、調印式を行いました。
また、2月18日(月)にJA紀の里代表理事組合長立ち会いのもと、調印式を行います。
有田川町での調印式

紀の川市での調印式
林ヶ峯地区では、あんぽ柿製品化の際のパッケージデザインをお手伝いしており、併せてデザイン案を披露しています。

また、1月30日(水)午後1時30分から、アグリコ12名と地域の方々、関係機関が出席し、活動報告会を開催しました。(財)和歌山社会経済研究所の進行により本年度のアグリコの活動報告と評価、今後の受入地の意向を確認しました。

報告会開催によって相互の意志確認が出来、また今後の体制づくりのために協定を交わすことで、地域と学生の交流が息の長い、着実な地域づくり・農村活性化につながって行くことを期待しています。
「文責 農業農村整備課 山端 徹」
当課では平成20年度から、県内大学生の行動力やアイデアを活用し、援農を基本とした継続的な中山間地域の支援体制構築に向け、地域との関係づくりや学生による地域支援活動等を行うシステムモデルの構築を目指すため、学生参画地域づくり体制サポートモデル事業を (財)和歌山社会経済研究所に委託しています。
(財)和歌山社会経済研究所は、平成20年度に和歌山大学経済学部ゼミの学生を中心に、学生の意識調査、受入地との意見交換を行いました。これがきっかけで農村の課題に気づいた学生が継続して援農活動に参加し、平成21年度に活性化のための組織化に向けた意識が芽生えました。
平成22年度には農業・農村交流サークル「アグリコ」を結成。平成23年度に和歌山大学から正式にサークルとして承認されました。
このたび、アグリコと受入地が、元気な地域づくりを目指して協定を締結することになりました。
締結先は、有田川町の沼谷区、紀の川市の林ヶ峯地区にある林ケ峯農産加工グループ「長寿の郷」、紀の里農業協同組合体験農業部会です。1月30日(水)午前10時30分から有田川町長、午後3時30分から紀の川市副市長立ち会いのもと、調印式を行いました。
また、2月18日(月)にJA紀の里代表理事組合長立ち会いのもと、調印式を行います。
有田川町での調印式

紀の川市での調印式
林ヶ峯地区では、あんぽ柿製品化の際のパッケージデザインをお手伝いしており、併せてデザイン案を披露しています。

また、1月30日(水)午後1時30分から、アグリコ12名と地域の方々、関係機関が出席し、活動報告会を開催しました。(財)和歌山社会経済研究所の進行により本年度のアグリコの活動報告と評価、今後の受入地の意向を確認しました。

報告会開催によって相互の意志確認が出来、また今後の体制づくりのために協定を交わすことで、地域と学生の交流が息の長い、着実な地域づくり・農村活性化につながって行くことを期待しています。
「文責 農業農村整備課 山端 徹」
2013年01月30日
柿の木を低くする栽培方法
寒い冬の季節、柿の木は葉を落とし、柿農家さんは樹の形を整える剪定作業を行います。
柿の木は高くなりやすく、柿農家さんは、脚立を使って高いところで作業を行わなければなりません。農家の高齢化も進んでいることから、安全で省力的な低い樹に仕立てることが求められています。
かき・もも研究所では、和歌山県の主力である『たねなし柿』(品種「刀根早生」、「平核無」)を対象に、初心者でも簡単に低く仕立てられる柿の樹形改造に取り組んでいます(農林水産省実用技術開発事業)。伊都振興局では、この樹形改造による栽培が実際に現場の園地で使えるのか、実証試験をおこなっています。樹形改造に取り組むには、冬場に骨格を作ることが必要であり、先日行った作業内容をレポートします。
◆1年目の実証園◆
まず、切り株の状態まで切り戻します。

これから樹を低くする柿園地です。枝が高く伸びています。

(1年目、最初の処理)
チェーンソーで切り株の状態まで切り戻しました。
そこまで切っても大丈夫?と思われるかもしれませんが、
柿の木は生命力が強く、翌年には太く旺盛な枝が伸びてきます。下の写真のように

(1年目夏の様子)
◆2年目の実証園◆

(2年目を迎えた木)
頑丈な枝を活用するため、切り株から伸びた良い枝を数本残し、骨格にできそうなものを2本選びます。

誘引用の鋼管を左右に設置、骨格となる枝は、45度くらいの角度に誘引、それぞれ反対方向に引っ張り一文字仕立てとします。
2年目で主な骨格が出来、3年目には再び柿の実を収穫することできます。

(3年目夏の木)
樹の高さは2mぐらいで、脚立を使わなくても手を伸ばせば作業できます。
作業性は格段に良くなります
実証園は伊都管内に3カ所設置しています。興味のある方は伊都振興局農業振興課、もしくはかき・もも研究所までご連絡下さい。
【文責 伊都振興局農業振興課 林】
柿の木は高くなりやすく、柿農家さんは、脚立を使って高いところで作業を行わなければなりません。農家の高齢化も進んでいることから、安全で省力的な低い樹に仕立てることが求められています。
かき・もも研究所では、和歌山県の主力である『たねなし柿』(品種「刀根早生」、「平核無」)を対象に、初心者でも簡単に低く仕立てられる柿の樹形改造に取り組んでいます(農林水産省実用技術開発事業)。伊都振興局では、この樹形改造による栽培が実際に現場の園地で使えるのか、実証試験をおこなっています。樹形改造に取り組むには、冬場に骨格を作ることが必要であり、先日行った作業内容をレポートします。
◆1年目の実証園◆
まず、切り株の状態まで切り戻します。

これから樹を低くする柿園地です。枝が高く伸びています。

(1年目、最初の処理)
チェーンソーで切り株の状態まで切り戻しました。
そこまで切っても大丈夫?と思われるかもしれませんが、
柿の木は生命力が強く、翌年には太く旺盛な枝が伸びてきます。下の写真のように

(1年目夏の様子)
◆2年目の実証園◆

(2年目を迎えた木)
頑丈な枝を活用するため、切り株から伸びた良い枝を数本残し、骨格にできそうなものを2本選びます。

誘引用の鋼管を左右に設置、骨格となる枝は、45度くらいの角度に誘引、それぞれ反対方向に引っ張り一文字仕立てとします。
2年目で主な骨格が出来、3年目には再び柿の実を収穫することできます。

(3年目夏の木)
樹の高さは2mぐらいで、脚立を使わなくても手を伸ばせば作業できます。
作業性は格段に良くなります

実証園は伊都管内に3カ所設置しています。興味のある方は伊都振興局農業振興課、もしくはかき・もも研究所までご連絡下さい。
【文責 伊都振興局農業振興課 林】
2013年01月30日
伊都地域の自然・文化を体験しませんか(小学生対象)
3/2(土)~3(日)、伊都地域の子どもたちの健全な育成を願う行政機関と民間団体が合同で「子ども地域体験交流事業」を行います。
子どもたちが伊都地域が有する自然・文化等のすばらしさを体験し環境保護について学び、子ども同士が交流する機会です
プログラム内容は、高野歴史講座、ごま豆腐づくり体験、環境保護講座、勤行体験、高野の火祭り見学などの予定です。
「子ども地域体験交流事業」
実施日 平成25年3月2日(土)~3日(日)
実施場所 高野山
参加対象 橋本市、伊都郡在住の小学校6年生又は5年生の児童
定員 30名(応募者多数の場合は抽選を行います)
参加費 子ども安全共済会会員は2,000円、非会員は3,000円
参加費には、宿泊料金、1日目遊食~2日目昼食代、各種体験プログラム費用、高野山内での移動費用、保険料が含まれます。
高野山までの電車代等の往復の経費は各自で負担となります。
申込方法 「はがき」、「封書」、又は「FAX」で郵便番号、住所、氏名、保護者氏名、学年、学校名、電話番号、所属子ども会名、希望集合・解散場所を記入のうえ、下記まで。
「伊都地方子ども育成事業実行委員会事務局」
〒648-8541橋本市市脇4丁目5番8号伊都振興局地域振興部総務県民課内
FAX 0736-33-4916(問い合わせ先電話番号 0736-33-4900)
集合場所 南海電鉄橋本駅9:45又は遍照尊院11:30
解散場所 遍照尊院14:40又は南海電鉄橋本駅16:36
申込期限 平成25年2月1日(金)
主催 伊都地方子ども育成事業実行委員会

文責 伊都振興局企画産業課 鍵本
子どもたちが伊都地域が有する自然・文化等のすばらしさを体験し環境保護について学び、子ども同士が交流する機会です

プログラム内容は、高野歴史講座、ごま豆腐づくり体験、環境保護講座、勤行体験、高野の火祭り見学などの予定です。
「子ども地域体験交流事業」
実施日 平成25年3月2日(土)~3日(日)
実施場所 高野山
参加対象 橋本市、伊都郡在住の小学校6年生又は5年生の児童
定員 30名(応募者多数の場合は抽選を行います)
参加費 子ども安全共済会会員は2,000円、非会員は3,000円
参加費には、宿泊料金、1日目遊食~2日目昼食代、各種体験プログラム費用、高野山内での移動費用、保険料が含まれます。
高野山までの電車代等の往復の経費は各自で負担となります。
申込方法 「はがき」、「封書」、又は「FAX」で郵便番号、住所、氏名、保護者氏名、学年、学校名、電話番号、所属子ども会名、希望集合・解散場所を記入のうえ、下記まで。
「伊都地方子ども育成事業実行委員会事務局」
〒648-8541橋本市市脇4丁目5番8号伊都振興局地域振興部総務県民課内
FAX 0736-33-4916(問い合わせ先電話番号 0736-33-4900)
集合場所 南海電鉄橋本駅9:45又は遍照尊院11:30
解散場所 遍照尊院14:40又は南海電鉄橋本駅16:36
申込期限 平成25年2月1日(金)
主催 伊都地方子ども育成事業実行委員会

文責 伊都振興局企画産業課 鍵本
2013年01月30日
2月7日「釜石の奇跡」片田敏孝教授の防災教育講演会【新宮市】
和歌山県教育委員会では、近い将来の発生が予想される東海・東南海・南海地震に備え、子どもたちに生き抜く力を付けさせる「わかやま学校防災力アップ事業」を実施しています。
この事業のモデル校である新宮市立光洋中学校と三輪崎小学校では、津波防災教育の第一人者である群馬大学大学院 片田敏孝教授のご指導とご助言を得ながら、防災教育に取り組んでいます。
このたび、新宮市教育委員会と新宮市の主催で、片田敏孝教授による津波防災教育講演会が開催されますのでお知らせします。

(クリックするとPDFファイルが開きます)
◆日 時: 平成25年2月7日(木) 19:00~ (開場 18:30)
◆場 所: 新宮市職業訓練センター (新宮市春日1-35【地図】)
◆講 師: 片田敏孝氏 (群馬大学大学院工学研究科教授・広域首都圏防災研究センター長)
◆備 考: 定員300名、入場無料、事前申込不要
東日本大震災では、片田敏孝教授の防災教育を受けた岩手県釜石市の子どもたちは、地震発生後すぐ自主的に高台へ避難したため、ほぼ全員が助かりました。
学校での防災教育が重要なのは言うまでもないのですが、片田教授は「家庭や地域との連携がなければ、子どもたちの命を救うことはできない」と説きます。
この講演会にはどなたでもご参加できますので、多くの方のご来場をお待ちしております。
お問い合わせは、新宮市教育委員会 学校教育課 (電話 0735-23-3364)までお願いします。
【参考サイト】
◆津波防災教育講演会(新宮市WEBサイト)
http://www.city.shingu.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=28419
◆釜石が繋いだ未来の希望 -子ども犠牲者ゼロまでの軌跡-(群馬大学)
http://www.ce.gunma-u.ac.jp/bousai/research02.html
◆わかやま学校防災力アップ事業研究授業発表会に行ってきました(当ブログ)
http://wakayamapr.ikora.tv/e838838.html
◆8月21日は「釜石の奇跡」片田敏孝教授による講演会【新宮市】(当ブログ)
http://wakayamapr.ikora.tv/e799353.html
◆新宮市職業訓練センターの地図
http://yahoo.jp/fZ5Z3q
【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】
この事業のモデル校である新宮市立光洋中学校と三輪崎小学校では、津波防災教育の第一人者である群馬大学大学院 片田敏孝教授のご指導とご助言を得ながら、防災教育に取り組んでいます。
このたび、新宮市教育委員会と新宮市の主催で、片田敏孝教授による津波防災教育講演会が開催されますのでお知らせします。

(クリックするとPDFファイルが開きます)
◆日 時: 平成25年2月7日(木) 19:00~ (開場 18:30)
◆場 所: 新宮市職業訓練センター (新宮市春日1-35【地図】)
◆講 師: 片田敏孝氏 (群馬大学大学院工学研究科教授・広域首都圏防災研究センター長)
◆備 考: 定員300名、入場無料、事前申込不要
東日本大震災では、片田敏孝教授の防災教育を受けた岩手県釜石市の子どもたちは、地震発生後すぐ自主的に高台へ避難したため、ほぼ全員が助かりました。
学校での防災教育が重要なのは言うまでもないのですが、片田教授は「家庭や地域との連携がなければ、子どもたちの命を救うことはできない」と説きます。
この講演会にはどなたでもご参加できますので、多くの方のご来場をお待ちしております。
お問い合わせは、新宮市教育委員会 学校教育課 (電話 0735-23-3364)までお願いします。
【参考サイト】
◆津波防災教育講演会(新宮市WEBサイト)
http://www.city.shingu.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=28419
◆釜石が繋いだ未来の希望 -子ども犠牲者ゼロまでの軌跡-(群馬大学)
http://www.ce.gunma-u.ac.jp/bousai/research02.html
◆わかやま学校防災力アップ事業研究授業発表会に行ってきました(当ブログ)
http://wakayamapr.ikora.tv/e838838.html
◆8月21日は「釜石の奇跡」片田敏孝教授による講演会【新宮市】(当ブログ)
http://wakayamapr.ikora.tv/e799353.html
◆新宮市職業訓練センターの地図
http://yahoo.jp/fZ5Z3q
【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】