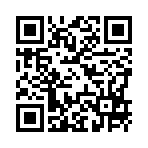2013年07月28日
8月3日(土)~4日(日)は、第9回串本まつり
第9回目串本まつりが、8月3日(土)~4日(日)開催されます。
本州最南端・串本の夏の風物詩として、多くの町民が参加し、昨年は約25,000人もの人出で賑わいました。
伝統の串本節おどり・花火大会、そしてライブやダンスパフォーマンスなど、町はお祭りムードに一色になります。
8月、新宮・東牟婁地方のトップを切り開催される花火大会でもある『串本まつり』にぜひお越しください!

(画像、串本町観光協会ホームページより)
以下、まつりの主なスケジュールです。
8月3日(土)
○町民総おどりの夕べ (雨天の場合8月4日(日)に順延)
【時間】18:15~19:30
【場所】ローソン串本店裏~串本港
○花火大会 (雨天の場合8月4日(日)、6日(月)に順延)
【時間】20:00~21:00 【打上数】約3,600発
【場所】串本港
【花火打上位置】
花火は串本港で打ち上げられるため、見通しが良さそうですね。
写真のように夜景と花火を楽しめる場所もありそうです。
8月4日(日)
○ふれあい広場
【時間】10:00~
【場所】文化センター駐車場
○ビンゴゲーム大会
【時間】13:00~
【場所】町立体育館
○鮎のつかみどり
【時間】15:00~
【場所】文化センター駐車場
○サマーBANDライブ
【時間】10:00~16:00
【場所】文化センター大ホール
○ダンス K-night
【時間】18:30~20:00
【会場周辺地図】http://www.kankou-kushimoto.jp/map/map_ah4.html
(参考)
串本町観光協会 http://www.kankou-kushimoto.jp/yotei.html
串本町役場 http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/
南紀熊野の旬情報瓦版「くまくま」8月号でも、新宮・東牟婁地方の花火情報をまとめています。
http://kumano-area.jp/kumakuma/index.html
(文責 東牟婁振興局企画産業課 吉中秀郎)
本州最南端・串本の夏の風物詩として、多くの町民が参加し、昨年は約25,000人もの人出で賑わいました。
伝統の串本節おどり・花火大会、そしてライブやダンスパフォーマンスなど、町はお祭りムードに一色になります。
8月、新宮・東牟婁地方のトップを切り開催される花火大会でもある『串本まつり』にぜひお越しください!

(画像、串本町観光協会ホームページより)
以下、まつりの主なスケジュールです。
8月3日(土)
○町民総おどりの夕べ (雨天の場合8月4日(日)に順延)
【時間】18:15~19:30
【場所】ローソン串本店裏~串本港
○花火大会 (雨天の場合8月4日(日)、6日(月)に順延)
【時間】20:00~21:00 【打上数】約3,600発
【場所】串本港
【花火打上位置】
花火は串本港で打ち上げられるため、見通しが良さそうですね。
写真のように夜景と花火を楽しめる場所もありそうです。
8月4日(日)
○ふれあい広場
【時間】10:00~
【場所】文化センター駐車場
○ビンゴゲーム大会
【時間】13:00~
【場所】町立体育館
○鮎のつかみどり
【時間】15:00~
【場所】文化センター駐車場
○サマーBANDライブ
【時間】10:00~16:00
【場所】文化センター大ホール
○ダンス K-night
【時間】18:30~20:00
【会場周辺地図】http://www.kankou-kushimoto.jp/map/map_ah4.html
(参考)
串本町観光協会 http://www.kankou-kushimoto.jp/yotei.html
串本町役場 http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/
南紀熊野の旬情報瓦版「くまくま」8月号でも、新宮・東牟婁地方の花火情報をまとめています。
http://kumano-area.jp/kumakuma/index.html
(文責 東牟婁振興局企画産業課 吉中秀郎)
2013年07月28日
東京の紀州散策(12)北区にあるその名もずばり「紀州神社」
毎日暑い日が続いています。今年の東京は、今のところ和歌山よりは少し気温が低いようですが、それでも日中はうだるような暑さです。そこで、今日は涼しいうちに出かけようと思い、朝6時に起きて、北区豊島(としま)にある「紀州神社」へ行ってきました。場所はJR京浜東北線の王子駅からだと歩いて20分、地下鉄南北線の王子神谷駅からは歩いて10分ぐらいの所にあります。
近くの豊島中央通り商店街は、ちょうど「豊島七夕祭り」の七夕飾りの期間中で、通りがとてもきれいに飾り付けられていました。人がいないのは朝7時30分ぐらいだからです。

商店街を北に抜けると、住宅地の中に紀州神社が見えてきました。

鳥居の右側には「紀州神社」と大きく書かれた石碑があります。私たち紀州の人間にとっては、こんなところで紀州に会えると、ちょっぴり誇らしくて、うれしくなってきます。

この紀州神社は、鎌倉時代後期の元亨年中(1321-24)に、紀州熊野から来た鈴木重尚(穂積二郎左ヱ門重尚)が地元の豊島氏とはかり、紀州名草郡の五十太祁神社(和歌山市の伊太祁曽神社のこと)を王子村に勧請したのがはじまりだそうです。その後天正年中(1573-92)に、豊島村と王子村の争いの中で何度か場所を移したのち、現在の豊島6丁目に落ち着いたとのことです。昔は「紀州明神」と呼ばれており、今でも地元の人々からは「紀州さま」と呼ばれ、親しまれているそうです。
祭神は、五十猛命(いたけるのみこと)、大屋津姫命(おおやつひめのみこと)、柧津姫命(つまつひめのみこと)、の3柱。当然、和歌山市の伊太祁曽神社の祭神と同じで、木の神様とされていることも伊太祁曽神社と同じです。
拝殿の額にも「紀州神社」の文字が。

こちらは拝殿の扉。熊野の守り神の三本足の「八咫烏(やたがらす)」の紋章があります。伊太祁曽神社と熊野三山がごっちゃになってきますが、堅いことは言わないでおきましょう。

以上が、紀州神社の訪問記です。こうやって見ると、昔から紀州の人々は全国各地で活躍していたことがわかります。そんな中でも、紀州の神社を祀って、故郷のことは忘れないという思いが強かったのではないでしょうか。今はすっかり都会となってしまい、紀州という名前だけが残っているのでしょうが、いにしえの紀州人の思いに少し心を打たれました。
皆さんもお暇なときに一度訪れてみてください。

(文責:東京事務所 林 清仁)
近くの豊島中央通り商店街は、ちょうど「豊島七夕祭り」の七夕飾りの期間中で、通りがとてもきれいに飾り付けられていました。人がいないのは朝7時30分ぐらいだからです。

商店街を北に抜けると、住宅地の中に紀州神社が見えてきました。

鳥居の右側には「紀州神社」と大きく書かれた石碑があります。私たち紀州の人間にとっては、こんなところで紀州に会えると、ちょっぴり誇らしくて、うれしくなってきます。

この紀州神社は、鎌倉時代後期の元亨年中(1321-24)に、紀州熊野から来た鈴木重尚(穂積二郎左ヱ門重尚)が地元の豊島氏とはかり、紀州名草郡の五十太祁神社(和歌山市の伊太祁曽神社のこと)を王子村に勧請したのがはじまりだそうです。その後天正年中(1573-92)に、豊島村と王子村の争いの中で何度か場所を移したのち、現在の豊島6丁目に落ち着いたとのことです。昔は「紀州明神」と呼ばれており、今でも地元の人々からは「紀州さま」と呼ばれ、親しまれているそうです。
祭神は、五十猛命(いたけるのみこと)、大屋津姫命(おおやつひめのみこと)、柧津姫命(つまつひめのみこと)、の3柱。当然、和歌山市の伊太祁曽神社の祭神と同じで、木の神様とされていることも伊太祁曽神社と同じです。
拝殿の額にも「紀州神社」の文字が。

こちらは拝殿の扉。熊野の守り神の三本足の「八咫烏(やたがらす)」の紋章があります。伊太祁曽神社と熊野三山がごっちゃになってきますが、堅いことは言わないでおきましょう。

以上が、紀州神社の訪問記です。こうやって見ると、昔から紀州の人々は全国各地で活躍していたことがわかります。そんな中でも、紀州の神社を祀って、故郷のことは忘れないという思いが強かったのではないでしょうか。今はすっかり都会となってしまい、紀州という名前だけが残っているのでしょうが、いにしえの紀州人の思いに少し心を打たれました。
皆さんもお暇なときに一度訪れてみてください。

(文責:東京事務所 林 清仁)