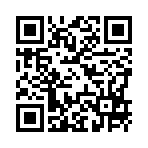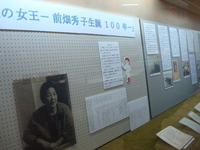2011年10月03日
「南方熊楠シンポジウム」レポートその2(10/2 明治大学)
ブログ編集長です。
昨日(10月2日)開催された「南方熊楠シンポジウム」のレポート(その2)をお届けします。
開演までの様子は、レポート(その1)をご覧ください。
いよいよ、13:30分よりシンポジウムが開演です。
司会の挨拶のあと、主催者を代表して、仁坂和歌山県知事が挨拶をしました。

知事は、「熊楠のフィールドが台風12号で大きな被害を受けたが、今まさによみがえろうとしている。」と報告。そのあと、今年5月の第62回全国植樹祭での和歌山県の「エコ」な取組をご紹介したあと、熊楠が「エコロジー」という概念を日本に紹介して100年の節目の年に、熊楠が時空を超えて語りかけているメッセージを知るきっかけにしてほしいと挨拶をしました。
続いて、共催の環境省地球環境局長の鈴木正規さんのご挨拶です。

鈴木局長のご両親は和歌山出身で、局長ご自身も湯浅町生まれとおっしゃったあと、熊楠はスケールが大きすぎて何をした人かわからないが、でもすごい。その熊楠を通して自然とどうつきあっていくのか、災害とどう向き合うのかを考えてほしいとご挨拶されました。
基調講演は、作家の荒俣宏さんです。その博学ぶりと多方面での造詣の深さから、まさに「現代の南方熊楠」と行っても過言ではないと思います。

ご講演では、「熊楠とエコロジーの物語~そこに愛と神があった」と題して、エコロジーという思想の系統と、その中での南方熊楠の位置づけなどをわかりやすくご説明くださいました。
話の要点は、以下のとおりでした。
●「エコロジー」という非常に難しい概念を100年前に提唱した熊楠の偉大さと、その生物学的・哲学的な意味
●「エコロジー」という言葉は現在「①生態学」「②自然と一緒に暮らそう運動」の2つの意味で使われている
●「エコロジー」思想の歴史と変遷。対象が植物から動物、さらには人間、地球へと広がり、次第に活動としての意味が付与されていく過程を紹介。
アレキサンダー・フォン・フンボルト(著書「コスモス」で地球規模の自然を記述)
ヘンリー・ソロー(1854 著書「ウォールデン~森の生活」「ロハス」誕生)
エルンスト・ヘッケル(1866「エコロジー」提唱、植物の共生関係)
カール・メビウス(カキの研究から食物連鎖)
エドアルト・ジュース(岩石と大地のあいだの生物層という考え方を提唱)
ステファン・フォーブス(湖はひとつの小宇宙)
南方熊楠(1910「エコロギー」植物棲態学)
ウラディーミル・ヴェルナドスキ(人間が作った地球「ノースフェア」)
レイチェル・カーソン(1962 DDTによる環境汚染告発、地球の資源は有限 運動としてのエコロジー誕生)
テイヤール・ド・シャルダン(地球は生物と合体、特に人類も合体するという思想)
ジェイムズ・ラブロック(1979 ガイア理論 地球は単一の生命体)
続いてご講演くださったのは以下の3名です。
①JT生命誌研究館館長 中村桂子さま
「生命誌の世界と熊楠」と題して、西洋、東洋、日本の思想を融合した熊楠の思想や、現代の機械的世界観ではなく複雑さに向き合う熊楠的考え方が21世紀を作り出すとご講演くださいました。
②元明治大学農学部教授 井川憲明さま
三重県熊野市出身の井川さんは、「熊楠のエコロジー思想」と題して、熊楠を「超感性人」と名付けて第6感に収まらない第7感の熊楠について熱弁をふるわれました。
③環境省参与 黒田大三郎さま
「熊楠の愛した”生物多様性の宝庫~熊野”」と題して、吉野熊野国立公園レンジャーとして2年半、熊野で過ごされた体験から、熊楠の愛した熊野の森や生き物の特徴などについてご講演いただきました。
これで、前半の講演会は終了。20分の休憩をはさんで座談会に入ります。休憩時間、2階の「熊楠と熊野」展示室はごったがえしていました。

いよいよ後半の座談会です。前半にご講演をいただいた4名に、仁坂知事を加えた5名で座談会を行いました。進行役はもちろん、「現代の熊楠」荒俣宏さまです。

テーマが「紀州的エコロジーのすすめ」という何とも漠然としたテーマでしたが、出演者がみなさんしっかりとしたご意見をお持ちで、聞いていて非常に楽しい座談会でした。
仁坂知事は、紀州・和歌山の紹介をしました。特に熊野については「やさしい混沌」と表現。森に覆われているが、人を拒絶するほどの険しさはないこと、熊野詣は「老若男女、貴賤を問わず、浄・不浄を問わず、信・不信を問わず」というよそ者を受け入れる風土があることを紹介したことは印象的でした。
環境省の黒田参与は、吉野熊野国立公園レンジャーとして新宮にいたころの想い出を、熊楠ほどには勉強しなかったが、那智山の動植物や再北限のサンゴなどを調査して回ったことを話されていました。
紀州熊野生まれの井川さんは、陸の孤島であった子供のころの熊野地域や、両親からさんざん聞かされた熊楠の話、牟婁地域の方言の話など、熊野に関するお話をしてくださいました。
JTの中村館長は、20世紀・科学から21世紀・文化への転換の必要性、その日本における原点が和歌山にあること、熊楠は洋の東西をミックス、宮沢賢治や柳田国男を生んだ岩手との共通点などについて興味深い話をお話しくださいました。
座談会はどんどん盛り上がり、荒俣さんが南方熊楠顕彰館の館長さんの豪快な逸話をお話しくださったり、知事は奇人の熊楠を支えた田辺の人々のあたたかさを話をしたりと、みなさんどんどん盛り上がってきて、最後は荒俣さんもまとめるのをあきらめて、これにて終了となりました。熊楠の懐の広さがゆえ話もどんどん広がったんだと思います。
なお、南方熊楠シンポジウムの中身をもっと知りたいという方は、12月11日(日)17日(土)14:00から NHK-Eテレで全国放送される予定です。座談会の模様を中心に放送されるそうなので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
昨日(10月2日)開催された「南方熊楠シンポジウム」のレポート(その2)をお届けします。
開演までの様子は、レポート(その1)をご覧ください。
いよいよ、13:30分よりシンポジウムが開演です。
司会の挨拶のあと、主催者を代表して、仁坂和歌山県知事が挨拶をしました。

知事は、「熊楠のフィールドが台風12号で大きな被害を受けたが、今まさによみがえろうとしている。」と報告。そのあと、今年5月の第62回全国植樹祭での和歌山県の「エコ」な取組をご紹介したあと、熊楠が「エコロジー」という概念を日本に紹介して100年の節目の年に、熊楠が時空を超えて語りかけているメッセージを知るきっかけにしてほしいと挨拶をしました。
続いて、共催の環境省地球環境局長の鈴木正規さんのご挨拶です。

鈴木局長のご両親は和歌山出身で、局長ご自身も湯浅町生まれとおっしゃったあと、熊楠はスケールが大きすぎて何をした人かわからないが、でもすごい。その熊楠を通して自然とどうつきあっていくのか、災害とどう向き合うのかを考えてほしいとご挨拶されました。
基調講演は、作家の荒俣宏さんです。その博学ぶりと多方面での造詣の深さから、まさに「現代の南方熊楠」と行っても過言ではないと思います。

ご講演では、「熊楠とエコロジーの物語~そこに愛と神があった」と題して、エコロジーという思想の系統と、その中での南方熊楠の位置づけなどをわかりやすくご説明くださいました。
話の要点は、以下のとおりでした。
●「エコロジー」という非常に難しい概念を100年前に提唱した熊楠の偉大さと、その生物学的・哲学的な意味
●「エコロジー」という言葉は現在「①生態学」「②自然と一緒に暮らそう運動」の2つの意味で使われている
●「エコロジー」思想の歴史と変遷。対象が植物から動物、さらには人間、地球へと広がり、次第に活動としての意味が付与されていく過程を紹介。
アレキサンダー・フォン・フンボルト(著書「コスモス」で地球規模の自然を記述)
ヘンリー・ソロー(1854 著書「ウォールデン~森の生活」「ロハス」誕生)
エルンスト・ヘッケル(1866「エコロジー」提唱、植物の共生関係)
カール・メビウス(カキの研究から食物連鎖)
エドアルト・ジュース(岩石と大地のあいだの生物層という考え方を提唱)
ステファン・フォーブス(湖はひとつの小宇宙)
南方熊楠(1910「エコロギー」植物棲態学)
ウラディーミル・ヴェルナドスキ(人間が作った地球「ノースフェア」)
レイチェル・カーソン(1962 DDTによる環境汚染告発、地球の資源は有限 運動としてのエコロジー誕生)
テイヤール・ド・シャルダン(地球は生物と合体、特に人類も合体するという思想)
ジェイムズ・ラブロック(1979 ガイア理論 地球は単一の生命体)
続いてご講演くださったのは以下の3名です。
①JT生命誌研究館館長 中村桂子さま
「生命誌の世界と熊楠」と題して、西洋、東洋、日本の思想を融合した熊楠の思想や、現代の機械的世界観ではなく複雑さに向き合う熊楠的考え方が21世紀を作り出すとご講演くださいました。
②元明治大学農学部教授 井川憲明さま
三重県熊野市出身の井川さんは、「熊楠のエコロジー思想」と題して、熊楠を「超感性人」と名付けて第6感に収まらない第7感の熊楠について熱弁をふるわれました。
③環境省参与 黒田大三郎さま
「熊楠の愛した”生物多様性の宝庫~熊野”」と題して、吉野熊野国立公園レンジャーとして2年半、熊野で過ごされた体験から、熊楠の愛した熊野の森や生き物の特徴などについてご講演いただきました。
これで、前半の講演会は終了。20分の休憩をはさんで座談会に入ります。休憩時間、2階の「熊楠と熊野」展示室はごったがえしていました。

いよいよ後半の座談会です。前半にご講演をいただいた4名に、仁坂知事を加えた5名で座談会を行いました。進行役はもちろん、「現代の熊楠」荒俣宏さまです。

テーマが「紀州的エコロジーのすすめ」という何とも漠然としたテーマでしたが、出演者がみなさんしっかりとしたご意見をお持ちで、聞いていて非常に楽しい座談会でした。
仁坂知事は、紀州・和歌山の紹介をしました。特に熊野については「やさしい混沌」と表現。森に覆われているが、人を拒絶するほどの険しさはないこと、熊野詣は「老若男女、貴賤を問わず、浄・不浄を問わず、信・不信を問わず」というよそ者を受け入れる風土があることを紹介したことは印象的でした。
環境省の黒田参与は、吉野熊野国立公園レンジャーとして新宮にいたころの想い出を、熊楠ほどには勉強しなかったが、那智山の動植物や再北限のサンゴなどを調査して回ったことを話されていました。
紀州熊野生まれの井川さんは、陸の孤島であった子供のころの熊野地域や、両親からさんざん聞かされた熊楠の話、牟婁地域の方言の話など、熊野に関するお話をしてくださいました。
JTの中村館長は、20世紀・科学から21世紀・文化への転換の必要性、その日本における原点が和歌山にあること、熊楠は洋の東西をミックス、宮沢賢治や柳田国男を生んだ岩手との共通点などについて興味深い話をお話しくださいました。
座談会はどんどん盛り上がり、荒俣さんが南方熊楠顕彰館の館長さんの豪快な逸話をお話しくださったり、知事は奇人の熊楠を支えた田辺の人々のあたたかさを話をしたりと、みなさんどんどん盛り上がってきて、最後は荒俣さんもまとめるのをあきらめて、これにて終了となりました。熊楠の懐の広さがゆえ話もどんどん広がったんだと思います。
なお、南方熊楠シンポジウムの中身をもっと知りたいという方は、12月
Posted by 広報ブログ編集長 at 12:15│Comments(2)
│人物
この記事へのコメント
10月2日のシンポジウムに参加させて頂いた者です。南方熊楠の魅力を再認識することが出来ました。有難う御座います。
一点、ご確認です。会場でNHK Eテレにて放送のアナウンスを聞きましたが、放送日は12月17日(土)14:00から、と手帳に記しております。11日ではなく17日の放送ではないでしょうか?
一点、ご確認です。会場でNHK Eテレにて放送のアナウンスを聞きましたが、放送日は12月17日(土)14:00から、と手帳に記しております。11日ではなく17日の放送ではないでしょうか?
Posted by 明楽 at 2011年10月10日 13:02
ご指摘有り難うございます。改めて確認したところ、仰るとおり12月17日(土)14:00からが正しいものです。17日と11日を聞き間違えたのだと思います。本文を訂正しておきますとともに、深くお詫びいたします。
Posted by 広報課ブログ編集長 at 2011年10月10日 13:40
at 2011年10月10日 13:40
 at 2011年10月10日 13:40
at 2011年10月10日 13:40※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。