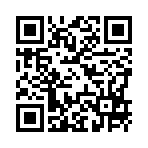2014年02月13日
2/10日本経済新聞のコラム「200年企業」で御坊市の堀河屋野村紹介!
今週月曜(2/10)の日本経済新聞(東京版では13面)のコラム「200年企業」で、「三ツ星醤油」で知られる御坊市の堀河屋野村さんが特集されていましたのでご紹介します。

記事には、堀河屋野村のこれまでの歩みが紹介されています。堀河屋を営む野村家はもともと熊野水軍の船大将の末裔で、江戸時代には廻船業を営んでいたのだそうです。そして元禄期に入り副業として行っていた醤油・味噌醸造業に転換したとのこと。現在の当主の野村太兵衛さんは、廻船業時代から数えて17代目、醸造業転業後からでも13代目にあたるそうですから、和歌山では現在残る最も古い蔵元ということになりますね。
戦後の高度経済成長期に、安い脱脂加工大豆を原料とした大量生産の醤油が出回る中、太兵衛さんは、赤字続きながらも、原料の大豆、麦、米はすべて国産、防腐剤や調味料は一切使わない手造り製法にこだわり続けたそうです。特に興味深かったのは、日本農林規格(JAS)認定をしても、手造りのため品質が微妙に異なることを理由に不認可となった際に、太兵衛さんが言った「わかってもらえないなら必要ない」という言葉です。お上の認可よりも手造りのこだわりを優先する姿勢が、全国の料理人の皆さんが「三ツ星醤油」を支持する理由なのでしょうね。
私も一昨年堀河屋野村さんにお邪魔した際には、醸造蔵で醤油造りの現場をを見学させていただき、そのこだわりの一端を知ることができました。
また、最近では、昨年12月に東京・銀座にオープンしたレストラン「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所 銀座店」の厨房で、「三ツ星醤油」がいくつも置かれているのを発見し、とても嬉しくなったのが記憶に残っています。

2012年からは息子の野村圭佑さんが、堀河屋18代目として働き始め、伝統を受け継いでおられるそうです。和歌山が誇る堀河屋野村の「三ツ星醤油」。これからもそのこだわりの伝統を末長く受け継いでいってほしいですね。
(文責:東京事務所 林 清仁)

記事には、堀河屋野村のこれまでの歩みが紹介されています。堀河屋を営む野村家はもともと熊野水軍の船大将の末裔で、江戸時代には廻船業を営んでいたのだそうです。そして元禄期に入り副業として行っていた醤油・味噌醸造業に転換したとのこと。現在の当主の野村太兵衛さんは、廻船業時代から数えて17代目、醸造業転業後からでも13代目にあたるそうですから、和歌山では現在残る最も古い蔵元ということになりますね。
戦後の高度経済成長期に、安い脱脂加工大豆を原料とした大量生産の醤油が出回る中、太兵衛さんは、赤字続きながらも、原料の大豆、麦、米はすべて国産、防腐剤や調味料は一切使わない手造り製法にこだわり続けたそうです。特に興味深かったのは、日本農林規格(JAS)認定をしても、手造りのため品質が微妙に異なることを理由に不認可となった際に、太兵衛さんが言った「わかってもらえないなら必要ない」という言葉です。お上の認可よりも手造りのこだわりを優先する姿勢が、全国の料理人の皆さんが「三ツ星醤油」を支持する理由なのでしょうね。
私も一昨年堀河屋野村さんにお邪魔した際には、醸造蔵で醤油造りの現場をを見学させていただき、そのこだわりの一端を知ることができました。
また、最近では、昨年12月に東京・銀座にオープンしたレストラン「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所 銀座店」の厨房で、「三ツ星醤油」がいくつも置かれているのを発見し、とても嬉しくなったのが記憶に残っています。

2012年からは息子の野村圭佑さんが、堀河屋18代目として働き始め、伝統を受け継いでおられるそうです。和歌山が誇る堀河屋野村の「三ツ星醤油」。これからもそのこだわりの伝統を末長く受け継いでいってほしいですね。
(文責:東京事務所 林 清仁)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。