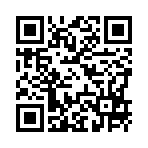2013年10月27日
東京の紀州散策(21)紀州藩赤坂邸を移築した日光田母沢御用邸
東京の紀州散策の第21回目は少し遠出をして、栃木県日光市にある「日光田母沢(たもざわ)御用邸記念公園」に行ってきましたので、そのレポートをお届けします。
今年5月に、このブログの「東京の紀州散策(2) 港区元赤坂の赤坂御用地と迎賓館赤坂離宮」の中で、現在の赤坂御用地はもとは紀州徳川家の江戸屋敷(赤坂邸)であったことや、現在赤坂御用地に残っている紀州徳川家の建物は「迎賓館東門」だけだということをご紹介しました。
ところが、あとから、紀州徳川家赤坂邸の建物が日光市にある旧日光田母沢御用邸に移築され現存していることを知りました。日光までは少し距離があるので行くのを躊躇していたのですが、秋の行楽シーズンになり、紅葉も見頃との情報を見ましたので、関東地方に久々に晴れ間が戻った今日(10/27)、日光まで出かけました。浅草駅から東武鉄道に乗って2時間余りで東武日光駅に到着。バスに乗り換えて国道沿いに西に約3km先、世界遺産・日光東照宮を通り過ぎ、田母沢バス停を降りてすぐのところに日光田母沢御用邸記念公園があります。
こちらの写真が正門です。敷地内には高い木々が生い茂り、とても閑静な雰囲気です。静養地としては最適な場所ですね。

こちらが正面入口の車寄せです。純和風の堂々とした造りが印象的です。

日光田母沢御用邸は、1899年(明治32年)に嘉仁親王(大正天皇)の夏のご静養地として造営され、1947年(昭和22年)に廃止されるまでの間、3代にわたる天皇・皇太子がご利用になった場所です。御用邸廃止後は、博物館や宿泊施設、研修施設として使用されていましたが、栃木県が3年の歳月をかけ、御用邸が最大の面積であった1921年(大正10年)の姿に復元・整備し、平成12年(2000)に記念公園として一般公開しました。
その規模は建築の床面積にして4,471平方メートル(約1,360坪)で、明治期に造営された御用邸の中でも最大規模であり、1棟の床面積としては我が国最大規模の木造建築物であり、現存する唯一の建物なのだそうです。
中核となっている建物は、紀州徳川家赤坂邸の中心部分で、1810年(天保11年)に建築されたものです。1872年(明治5年)に皇室に献上された後は、赤坂離宮、仮皇居、東宮御所として、一部増築しながら使用されていましたが、田母沢御用邸の造営のため、1898年(明治31年)に解体され、移築されました。その際に、もともとこの地にあった小林家別邸の建物も取り込み、一つの建物として作られたのです。さらに、1918年(大正7年)から大規模な増改築が行われて、現在の姿となっています。その結果、一つの建物の中に江戸・明治・大正の3つの時代の建築様式がみられるとても貴重な建造物として、2003年(平成19年)には、国の重要文化財に指定されています。
パンフレットには場所ごとの建築」年代が記されていますので、転載させていただきます。紀州徳川家赤坂邸の部分は赤色の部分で、この建物で唯一3階となっているところです。1階が天皇陛下が日常的な公務をお執りになる御座所と御学問所、2階が天皇陛下の寝室など、3階が展望室ですから、まさに御用邸の中核として使われていたことがわかります。

(画像をクリックすると拡大表示します。)
さて、前置きが長くなりましたが、紀州藩邸移築部分の内部をご紹介しましょう。
こちらが、1階の「御座所(ござしょ)」(奥)と「御次の間」。天皇陛下が日常的な公務をお執りになった場所です。

1階から2階に階段を上ってきたところ。

2階の「御寝室」(奥)と「御次の間」。寝室には照明器具はなく、燭台を用いていたそうです。


寝室の隣にある「劍璽(けんじ)の間」。「三種の神器」のうち、剣と勾玉を奉安する場所です。

2階の「御日拝所」。ご先祖を遙拝された場所です。

3階の「御展望室」は、普段は非公開です。急な階段を上っていきます。

紀州藩邸で使われていた襖絵もそのまま使用されていました。

こちらは、庭から見た紀州藩邸移築部分です。紀州徳川家の栄華が忍ばれます。

庭園の木々は少しずつ色づいていました。あと1週間もすれば紅葉がとてもきれいでしょうね。

以上が、日光田母沢御用邸のレポートです。今回は紀州藩邸部分をご紹介しましたが、その他の部分も、時代ごとの特徴があって、見所満載です。日光観光といえば、どうしても世界遺産の日光東照宮や、その先の中禅寺湖、華厳の滝がメインになってしまいますが、日光田母沢御用邸にも一度立ち寄ってみてください。
(文責:東京事務所 林 清仁)
今年5月に、このブログの「東京の紀州散策(2) 港区元赤坂の赤坂御用地と迎賓館赤坂離宮」の中で、現在の赤坂御用地はもとは紀州徳川家の江戸屋敷(赤坂邸)であったことや、現在赤坂御用地に残っている紀州徳川家の建物は「迎賓館東門」だけだということをご紹介しました。
ところが、あとから、紀州徳川家赤坂邸の建物が日光市にある旧日光田母沢御用邸に移築され現存していることを知りました。日光までは少し距離があるので行くのを躊躇していたのですが、秋の行楽シーズンになり、紅葉も見頃との情報を見ましたので、関東地方に久々に晴れ間が戻った今日(10/27)、日光まで出かけました。浅草駅から東武鉄道に乗って2時間余りで東武日光駅に到着。バスに乗り換えて国道沿いに西に約3km先、世界遺産・日光東照宮を通り過ぎ、田母沢バス停を降りてすぐのところに日光田母沢御用邸記念公園があります。
こちらの写真が正門です。敷地内には高い木々が生い茂り、とても閑静な雰囲気です。静養地としては最適な場所ですね。

こちらが正面入口の車寄せです。純和風の堂々とした造りが印象的です。

日光田母沢御用邸は、1899年(明治32年)に嘉仁親王(大正天皇)の夏のご静養地として造営され、1947年(昭和22年)に廃止されるまでの間、3代にわたる天皇・皇太子がご利用になった場所です。御用邸廃止後は、博物館や宿泊施設、研修施設として使用されていましたが、栃木県が3年の歳月をかけ、御用邸が最大の面積であった1921年(大正10年)の姿に復元・整備し、平成12年(2000)に記念公園として一般公開しました。
その規模は建築の床面積にして4,471平方メートル(約1,360坪)で、明治期に造営された御用邸の中でも最大規模であり、1棟の床面積としては我が国最大規模の木造建築物であり、現存する唯一の建物なのだそうです。
中核となっている建物は、紀州徳川家赤坂邸の中心部分で、1810年(天保11年)に建築されたものです。1872年(明治5年)に皇室に献上された後は、赤坂離宮、仮皇居、東宮御所として、一部増築しながら使用されていましたが、田母沢御用邸の造営のため、1898年(明治31年)に解体され、移築されました。その際に、もともとこの地にあった小林家別邸の建物も取り込み、一つの建物として作られたのです。さらに、1918年(大正7年)から大規模な増改築が行われて、現在の姿となっています。その結果、一つの建物の中に江戸・明治・大正の3つの時代の建築様式がみられるとても貴重な建造物として、2003年(平成19年)には、国の重要文化財に指定されています。
パンフレットには場所ごとの建築」年代が記されていますので、転載させていただきます。紀州徳川家赤坂邸の部分は赤色の部分で、この建物で唯一3階となっているところです。1階が天皇陛下が日常的な公務をお執りになる御座所と御学問所、2階が天皇陛下の寝室など、3階が展望室ですから、まさに御用邸の中核として使われていたことがわかります。

(画像をクリックすると拡大表示します。)
さて、前置きが長くなりましたが、紀州藩邸移築部分の内部をご紹介しましょう。
こちらが、1階の「御座所(ござしょ)」(奥)と「御次の間」。天皇陛下が日常的な公務をお執りになった場所です。

1階から2階に階段を上ってきたところ。

2階の「御寝室」(奥)と「御次の間」。寝室には照明器具はなく、燭台を用いていたそうです。


寝室の隣にある「劍璽(けんじ)の間」。「三種の神器」のうち、剣と勾玉を奉安する場所です。

2階の「御日拝所」。ご先祖を遙拝された場所です。

3階の「御展望室」は、普段は非公開です。急な階段を上っていきます。

紀州藩邸で使われていた襖絵もそのまま使用されていました。

こちらは、庭から見た紀州藩邸移築部分です。紀州徳川家の栄華が忍ばれます。

庭園の木々は少しずつ色づいていました。あと1週間もすれば紅葉がとてもきれいでしょうね。

以上が、日光田母沢御用邸のレポートです。今回は紀州藩邸部分をご紹介しましたが、その他の部分も、時代ごとの特徴があって、見所満載です。日光観光といえば、どうしても世界遺産の日光東照宮や、その先の中禅寺湖、華厳の滝がメインになってしまいますが、日光田母沢御用邸にも一度立ち寄ってみてください。
(文責:東京事務所 林 清仁)
Posted by 広報ブログ編集長 at 23:39│Comments(0)
│東京事務所通信
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。