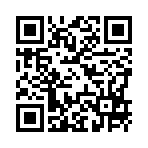2012年07月24日
有田川の河口付近で干潟観察会が行われました(7月22日)
有田振興局企画産業課です。
有田市の有田川河口付近には、小さな干潟があります。あまり大きくないので目立たないのですが、
環境省の「日本の重要湿地500」
にも選定されている素晴らしい干潟なんです。
ここで、和歌山大学教育学部の古賀庸憲教授と生物学教室の学生さん達が中心となって、干潟観察会が行われました。

一般参加者を含めて40名ほどが集まり、子どもさんもたくさん参加していました。
最初に、古賀教授から概要説明がありました。
以前、この辺一体はプレジャーボートがたくさん係留されていたため、マリーナの整備が計画されたそうです。
しかし、ここは貴重な生物が生息している湿地であるため、湿地の保存を求めて声を上げたところ、計画が撤回され、今の湿地が残されることとなったとのことです。

当日は、割と雲が多く、日差しも適度に弱まり、観察には絶好の気候でした。
湿地に向かって歩道を歩いていると、歩道の下にアシハラガニやチゴガニがちょこちょこと動いているのが見えます。

(アシハラガニ)
いざ湿地に降りてみると…。いるわいるわ、カニさんの大集団です。ハクセンシオマネキやチゴガニは、静かに見守っているとハサミを振りはじめます。これはウエイビングという求愛行動だそうで、見ていてとてもかわいかったです。

(体が大きくて片方のハサミが大きいのがハクセンシオマネキの雄、
体が小さくて両方のハサミが同じ大きさなのがハクセンシオマネキの雌やチゴガニ)
この他、マメコブシガニ、ケフサイソガニなどのカニ類や、ハゼやゴカイの仲間も見つけることができました。マメコブシガニは横歩きではなくて前に歩くし、ハゼは手で撫でてもジッとしていてなかなか動かなかったので、とても面白かったです。
また、今回は見つけられなかったのですが、この湿地には絶滅危惧種とされているコゲツノブエという巻き貝もいるそうです。

(中央はウミニナなどの巻き貝とその貝殻を背負ったヤドカリ、
左上はハゼの仲間、左下はゴカイの仲間、右下はマメコブシガニ)

(コゲツノブエ(和歌山大学教育学部・古賀教授に写真を提供していただきました))
古賀教授によると、このような貴重な湿地があることを地元の人も意外と知らないようなので、10年前から観察会を始めたとのことです。
湿地なので地面が軟らかい所も多く、ぬかるみで足が抜けなくなったり、転んで泥んこになっている子どももいましたが、みんな楽しそうに観察していました。
昨年の台風12号の豪雨により、有田川も流れが大きく変わったりしている所もあるのですが、小さな生き物達がこの湿地で豪雨にも負けずに頑張って生きていることに感動しました。
意外と身近な場所に色んな生き物がいますので、皆さんも観察に出かけてみませんか? でも、観察した生き物は、元の場所に返してあげてね。
(文責:有田振興局企画産業課 古糸昭洋)
有田市の有田川河口付近には、小さな干潟があります。あまり大きくないので目立たないのですが、
環境省の「日本の重要湿地500」
にも選定されている素晴らしい干潟なんです。
ここで、和歌山大学教育学部の古賀庸憲教授と生物学教室の学生さん達が中心となって、干潟観察会が行われました。

一般参加者を含めて40名ほどが集まり、子どもさんもたくさん参加していました。
最初に、古賀教授から概要説明がありました。
以前、この辺一体はプレジャーボートがたくさん係留されていたため、マリーナの整備が計画されたそうです。
しかし、ここは貴重な生物が生息している湿地であるため、湿地の保存を求めて声を上げたところ、計画が撤回され、今の湿地が残されることとなったとのことです。

当日は、割と雲が多く、日差しも適度に弱まり、観察には絶好の気候でした。
湿地に向かって歩道を歩いていると、歩道の下にアシハラガニやチゴガニがちょこちょこと動いているのが見えます。

(アシハラガニ)
いざ湿地に降りてみると…。いるわいるわ、カニさんの大集団です。ハクセンシオマネキやチゴガニは、静かに見守っているとハサミを振りはじめます。これはウエイビングという求愛行動だそうで、見ていてとてもかわいかったです。

(体が大きくて片方のハサミが大きいのがハクセンシオマネキの雄、
体が小さくて両方のハサミが同じ大きさなのがハクセンシオマネキの雌やチゴガニ)
この他、マメコブシガニ、ケフサイソガニなどのカニ類や、ハゼやゴカイの仲間も見つけることができました。マメコブシガニは横歩きではなくて前に歩くし、ハゼは手で撫でてもジッとしていてなかなか動かなかったので、とても面白かったです。
また、今回は見つけられなかったのですが、この湿地には絶滅危惧種とされているコゲツノブエという巻き貝もいるそうです。

(中央はウミニナなどの巻き貝とその貝殻を背負ったヤドカリ、
左上はハゼの仲間、左下はゴカイの仲間、右下はマメコブシガニ)

(コゲツノブエ(和歌山大学教育学部・古賀教授に写真を提供していただきました))
古賀教授によると、このような貴重な湿地があることを地元の人も意外と知らないようなので、10年前から観察会を始めたとのことです。
湿地なので地面が軟らかい所も多く、ぬかるみで足が抜けなくなったり、転んで泥んこになっている子どももいましたが、みんな楽しそうに観察していました。
昨年の台風12号の豪雨により、有田川も流れが大きく変わったりしている所もあるのですが、小さな生き物達がこの湿地で豪雨にも負けずに頑張って生きていることに感動しました。
意外と身近な場所に色んな生き物がいますので、皆さんも観察に出かけてみませんか? でも、観察した生き物は、元の場所に返してあげてね。
(文責:有田振興局企画産業課 古糸昭洋)
Posted by ふっちゃん at 15:32│Comments(0)
│地域情報
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。