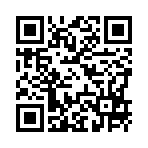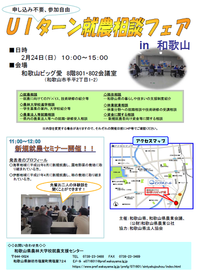2012年08月21日
県立新翔高校で高校生防災スクールが開催されました【レポート】
和歌山県教育委員会では、夏休み期間中、県内5つの高校にて「高校生防災スクール」を開催しています。
これは、将来の地域防災リーダーを育成するために、平成16年から毎年開催しているものです。
東牟婁振興局管内では、新宮市佐野にある県立新翔高等学校で本日開催されましたので、簡単ですがレポートします。
新翔高校の高校生防災スクールは、朝8時30分に始まりました。
参加者は、東牟婁管内の中高生と引率の教員合わせて150名ほど。
テレビ和歌山のスタッフも取材に訪れていました。

開会式の後、岩手県山田町総務課危機管理室の道又城さんが、「東日本大震災の教訓と若者に期待すること」として講演されました。

山田町は、東日本大震災発災後に津波に襲われ、775名の方が亡くなり、また町内の半分近くの家屋が被災したそうです。
道又さんは発災後、避難所となった小学校で避難所運営に関わりましたが、暖房が足らず、また学校には食糧や毛布も備蓄されておらず、集まってきた500人近くの避難者を職員2名だけで把握しなければならないなど、とても苦労したそうです。
そんな中で、地元の中高生が物資の仕分けや力仕事などで率先して活動してくれたり、和歌山県からも日本赤十字社和歌山県支部や市町村職員が駆けつけてくれてとても助かったとおっしゃってました。

最後に、個々で非常持出袋を用意しておくこと、避難所運営には地域の人たちの力が不可欠なこと、長引く避難生活には避難者に役割を分担させることが必要なこと、被災地から学ぶ際は良かった点よりも改善すべき点に注目することが大事だと締めくくりました。

続いて、災害ボランティアセンター運営訓練が始まりました。
まずは住民への「声かけ・聞き取り訓練」です。
受付で渡された地図を元に、事前にお願いしていた高齢者のご自宅を訪問します。

訪問先では、お名前やご住所、地震が発生した際に不安に思うこと、体の調子や家具類の固定状況などについて質問してました。

調理教室では、新翔高校の生徒による「炊き出し・配膳訓練」が行われました。
カレー味のアルファ米もあり、いい香りが食堂に漂っていました。


こちらは、東牟婁振興局に置いてある地震体験車「紀州なまず号」です。
和歌山県に配置されてから20年目になる車体ですが、なんとか現役で頑張っています。
地域のイベントや防災訓練で体験できますので、ご希望の方は、市町村役場や消防署にご相談ください。
続いて、防災実技講習と普通救命講習に移ります。

こちらは、三角巾を使った応急手当の講習です。
三角巾が1枚あるだけで、いろんなケガに対応できるのはすごいですね。

こちらは、段ボールとダブルクリップを使ったパーティション(仕切り板)の組立講習です。
避難所生活でも、ある程度のプライバシーは守られなくてはなりません。
なお、このメニューは今年度初めて採用されたそうです。

武道場では、搬送法の講習が行われていました。
これは、竹竿と毛布を利用した搬送法です。
事前に指導を受けた新翔高校の生徒が、他校の生徒を指導していました。

こちらは、新宮市消防本部の職員による普通救命講習です。
知識として知っていても、実際に体を動かしてやってみないと、自分のものにはなりません。
皆さんも、救命講習は定期的に受講してくださいね
災害は起きないに越したことはないのですが、東海・東南海・南海地震は、近い将来必ず発生します。
そのとき、地域の防災リーダーとして活躍するのは、現在の子どもたちだと言われています。
より多くの子どもたちが、このような防災教育を受けて、将来の和歌山県を背負って立つ大人になってくれることを期待しています
【参考URL】
和歌山県教育委員会: http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500900/
【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】
これは、将来の地域防災リーダーを育成するために、平成16年から毎年開催しているものです。
東牟婁振興局管内では、新宮市佐野にある県立新翔高等学校で本日開催されましたので、簡単ですがレポートします。
新翔高校の高校生防災スクールは、朝8時30分に始まりました。
参加者は、東牟婁管内の中高生と引率の教員合わせて150名ほど。
テレビ和歌山のスタッフも取材に訪れていました。

開会式の後、岩手県山田町総務課危機管理室の道又城さんが、「東日本大震災の教訓と若者に期待すること」として講演されました。

山田町は、東日本大震災発災後に津波に襲われ、775名の方が亡くなり、また町内の半分近くの家屋が被災したそうです。
道又さんは発災後、避難所となった小学校で避難所運営に関わりましたが、暖房が足らず、また学校には食糧や毛布も備蓄されておらず、集まってきた500人近くの避難者を職員2名だけで把握しなければならないなど、とても苦労したそうです。
そんな中で、地元の中高生が物資の仕分けや力仕事などで率先して活動してくれたり、和歌山県からも日本赤十字社和歌山県支部や市町村職員が駆けつけてくれてとても助かったとおっしゃってました。

最後に、個々で非常持出袋を用意しておくこと、避難所運営には地域の人たちの力が不可欠なこと、長引く避難生活には避難者に役割を分担させることが必要なこと、被災地から学ぶ際は良かった点よりも改善すべき点に注目することが大事だと締めくくりました。

続いて、災害ボランティアセンター運営訓練が始まりました。
まずは住民への「声かけ・聞き取り訓練」です。
受付で渡された地図を元に、事前にお願いしていた高齢者のご自宅を訪問します。

訪問先では、お名前やご住所、地震が発生した際に不安に思うこと、体の調子や家具類の固定状況などについて質問してました。

調理教室では、新翔高校の生徒による「炊き出し・配膳訓練」が行われました。
カレー味のアルファ米もあり、いい香りが食堂に漂っていました。


こちらは、東牟婁振興局に置いてある地震体験車「紀州なまず号」です。
和歌山県に配置されてから20年目になる車体ですが、なんとか現役で頑張っています。
地域のイベントや防災訓練で体験できますので、ご希望の方は、市町村役場や消防署にご相談ください。
続いて、防災実技講習と普通救命講習に移ります。

こちらは、三角巾を使った応急手当の講習です。
三角巾が1枚あるだけで、いろんなケガに対応できるのはすごいですね。

こちらは、段ボールとダブルクリップを使ったパーティション(仕切り板)の組立講習です。
避難所生活でも、ある程度のプライバシーは守られなくてはなりません。
なお、このメニューは今年度初めて採用されたそうです。

武道場では、搬送法の講習が行われていました。
これは、竹竿と毛布を利用した搬送法です。
事前に指導を受けた新翔高校の生徒が、他校の生徒を指導していました。

こちらは、新宮市消防本部の職員による普通救命講習です。
知識として知っていても、実際に体を動かしてやってみないと、自分のものにはなりません。
皆さんも、救命講習は定期的に受講してくださいね

災害は起きないに越したことはないのですが、東海・東南海・南海地震は、近い将来必ず発生します。
そのとき、地域の防災リーダーとして活躍するのは、現在の子どもたちだと言われています。
より多くの子どもたちが、このような防災教育を受けて、将来の和歌山県を背負って立つ大人になってくれることを期待しています

【参考URL】
和歌山県教育委員会: http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500900/
【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】
Posted by くまくま at 17:52│Comments(0)
│県の施策
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。