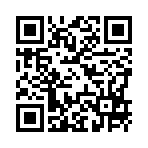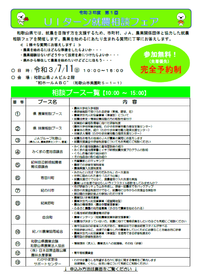2012年05月17日
熊野古道歴史散策ツアーが行われました(5/14)
有田振興局企画産業課です。
5月14日(月)に、京都聖護院門跡の宮城泰年門主とともに、湯浅町から有田市にかけての熊野古道を歩き、その歴史を訪ねるツアーが行われました。
ツアー一行は、JR湯浅駅から、勝楽寺に向けて出発しました。勝楽寺には、阿弥陀如来座像など8体の重要文化財が安置されており、これを拝観させていただきました。
続いて、一行は深専寺に移動。近くの立石道標脇の一角は、聖護院や三宝院の門跡が護摩を焚いた跡だそうで、1839年には聖護院の宮が、大峰峰入りの帰路に深専寺で休息と食事をされたそうです。この故事にちなみ、実に173年振りに聖護院門主が深専寺を訪れ、境内で護摩供養が行われました。隣の幼稚園からもたくさんの園児さんが来られ、珍しそうに見学していました。
ちなみに、深専寺には「津波心得の記」という安政南海地震の訓戒の石碑もあります。

一行は、深専寺を出て、昼食を摂ったあと、再び熊野古道を散策。弘法井戸、逆川王子、糸我峠、糸我王子を経て、有田市の糸我稲荷に入りました。
糸我稲荷は、京都伏見稲荷神社よりも約60年も早い白雉3年の創建であり、日本最古の稲荷神社として有名です。

糸我稲荷を参拝したあと、隣の糸我小学校に場所を移し、京都聖護院門跡の宮城泰年門主による「熊野古道・修験修行の道」と題した講演が行われました。
京都聖護院や修験道の歴史をはじめ、熊野古道や有田地方との関わりなど、宮城門主が柔和な口調で語られました。

宮城門主の講演後、得生寺で行われた来迎会式を見学しました。
この得生寺の会式は、中将姫の命日にちなみ、毎年5月13日と14日に行われる行事で、県の無形民俗文化財に指定されています。14日には地元の子ども達が演じる「二十五菩薩の渡御」があり、開山堂から本堂へ練り歩く姿は見応えがあります。

すぐ近くにある「くまの古道歴史民族資料館」も各々見学した後、JR宮原駅まで歩き、ツアーは終了しました。
今回のコースは、熊野古道・紀伊路の一部となっています。今日のツアーでは、途中で護摩供養や講演会、会式などのイベントがあったため、JR湯浅駅を朝9時30分に出発し、JR宮原駅には夕方5時頃の到着となりました。
通常であれば半日程度で散策を楽しめるコースですので、是非歩いてみてください。
(文責:有田振興局企画産業課 古糸昭洋)
5月14日(月)に、京都聖護院門跡の宮城泰年門主とともに、湯浅町から有田市にかけての熊野古道を歩き、その歴史を訪ねるツアーが行われました。
ツアー一行は、JR湯浅駅から、勝楽寺に向けて出発しました。勝楽寺には、阿弥陀如来座像など8体の重要文化財が安置されており、これを拝観させていただきました。
続いて、一行は深専寺に移動。近くの立石道標脇の一角は、聖護院や三宝院の門跡が護摩を焚いた跡だそうで、1839年には聖護院の宮が、大峰峰入りの帰路に深専寺で休息と食事をされたそうです。この故事にちなみ、実に173年振りに聖護院門主が深専寺を訪れ、境内で護摩供養が行われました。隣の幼稚園からもたくさんの園児さんが来られ、珍しそうに見学していました。
ちなみに、深専寺には「津波心得の記」という安政南海地震の訓戒の石碑もあります。

一行は、深専寺を出て、昼食を摂ったあと、再び熊野古道を散策。弘法井戸、逆川王子、糸我峠、糸我王子を経て、有田市の糸我稲荷に入りました。
糸我稲荷は、京都伏見稲荷神社よりも約60年も早い白雉3年の創建であり、日本最古の稲荷神社として有名です。

糸我稲荷を参拝したあと、隣の糸我小学校に場所を移し、京都聖護院門跡の宮城泰年門主による「熊野古道・修験修行の道」と題した講演が行われました。
京都聖護院や修験道の歴史をはじめ、熊野古道や有田地方との関わりなど、宮城門主が柔和な口調で語られました。

宮城門主の講演後、得生寺で行われた来迎会式を見学しました。
この得生寺の会式は、中将姫の命日にちなみ、毎年5月13日と14日に行われる行事で、県の無形民俗文化財に指定されています。14日には地元の子ども達が演じる「二十五菩薩の渡御」があり、開山堂から本堂へ練り歩く姿は見応えがあります。

すぐ近くにある「くまの古道歴史民族資料館」も各々見学した後、JR宮原駅まで歩き、ツアーは終了しました。
今回のコースは、熊野古道・紀伊路の一部となっています。今日のツアーでは、途中で護摩供養や講演会、会式などのイベントがあったため、JR湯浅駅を朝9時30分に出発し、JR宮原駅には夕方5時頃の到着となりました。
通常であれば半日程度で散策を楽しめるコースですので、是非歩いてみてください。
(文責:有田振興局企画産業課 古糸昭洋)
Posted by ふっちゃん at 09:24│Comments(0)
│イベント・地域振興
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。