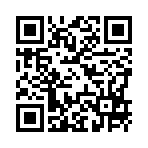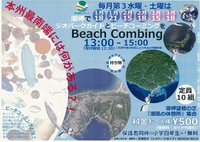2012年05月13日
紀州東照宮の「和歌祭」華やかに開催されました!
今日(5/13)、和歌山市の紀州東照宮の大祭「和歌祭」です。私も長い間和歌山に住んでいますが、これまで和歌祭には行ったことがなかったので、一度行ってみようと和歌浦にある紀州東照宮に出かけました。
このお祭りは、江戸時代初めの元和8年(1622年)に始まったそうです。今年が2012年ですから今から390年前になりますね。徳川家康公を祀る紀州東照宮が紀州藩祖徳川頼宣公によって創建されたのが前年の元和7年(1621)ですので、その翌年には始まっていることになります。家康公のお祭りですから、江戸時代はたいへん盛大だったようで、日本三大祭りと呼ばれていたそうです。その後、第二次大戦など、これまで2度の中断はあったそうですが、和歌祭保存会がつくられるなどして、390年の伝統を今日につたえている貴重な祭りでもあります。全国にある東照宮でもこのような祭りが残っているのは、日光と紀州だけだそうです。
祭りはまず、家康公の霊を乗せた御輿が東照宮の108段の階段を下りる「御輿おろし」から始まります。「御輿おろし」を前に階段前の参道も、両側の柵の外側も見物客でぎっしり埋め尽くされています。

11時30分、いよいよ「御輿おろし」が始まりました。お囃子の音とともに、御輿をかついだ人たちが、急な階段をゆっくり降りてきます。この様子は動画でご覧ください。
階段を下りた御輿は、若者たちのかけ声とともに参道を練り歩きます。ものすごい熱気です。

東照宮前の広場でもう一度、御輿かつぎが繰り広げられます。こちらも動画でどうぞ!!
この後、正午から渡御行列が始まりました。渡御行列は、御輿を中心に太鼓や雑賀踊、薙刀振りなどが和歌浦を練り歩くもので、東照宮から和歌浦漁港前、片男波を経由してあしべ橋を渡り、再び東照宮へ戻ってきます。途中に設置された5ヶ所のポイントではそれぞれの芸ごとに演舞が披露されるのだそうです。
行列奉行・打鉦に続いて、五色の旗がスタートです。青空に映えてきれいですね。

御輿は近くで見るとものすごい迫力と熱気です。

こちらは「ギャル御輿」。和歌山ご当地アイドルの「ZagaDa」が参加しています。

次は「子ども御輿」。担いでいるのは宝船のようですね。葵のご紋が輝いています。

続いては「御所御輿」。子どもたちが引っ張り、横にはお母さんたちがぴったり寄り添っています。

御輿の後を、東照宮の宮司さんをはじめ神官が馬に乗って続きます。馬の渡御は10年ぶりだそうです。

こちらは「相撲取り」。大人に混じって子どもの相撲取りもいます。かわいいですね。

こちらは「連尺」。行商の反物売りです。

私が滞在したのはここまでです。時間の都合でここで失礼しましたが、まだまだ行列は続きます。
和歌祭の時代絵巻の雰囲気、少しは感じていただけましたでしょうか。私にとっては初体験でしたが、390年間続く和歌山の風物詩を、今後も大事に守っていきたいな、と強く感じました。
(文責:広報課 林 清仁)
このお祭りは、江戸時代初めの元和8年(1622年)に始まったそうです。今年が2012年ですから今から390年前になりますね。徳川家康公を祀る紀州東照宮が紀州藩祖徳川頼宣公によって創建されたのが前年の元和7年(1621)ですので、その翌年には始まっていることになります。家康公のお祭りですから、江戸時代はたいへん盛大だったようで、日本三大祭りと呼ばれていたそうです。その後、第二次大戦など、これまで2度の中断はあったそうですが、和歌祭保存会がつくられるなどして、390年の伝統を今日につたえている貴重な祭りでもあります。全国にある東照宮でもこのような祭りが残っているのは、日光と紀州だけだそうです。
祭りはまず、家康公の霊を乗せた御輿が東照宮の108段の階段を下りる「御輿おろし」から始まります。「御輿おろし」を前に階段前の参道も、両側の柵の外側も見物客でぎっしり埋め尽くされています。

11時30分、いよいよ「御輿おろし」が始まりました。お囃子の音とともに、御輿をかついだ人たちが、急な階段をゆっくり降りてきます。この様子は動画でご覧ください。
階段を下りた御輿は、若者たちのかけ声とともに参道を練り歩きます。ものすごい熱気です。

東照宮前の広場でもう一度、御輿かつぎが繰り広げられます。こちらも動画でどうぞ!!
この後、正午から渡御行列が始まりました。渡御行列は、御輿を中心に太鼓や雑賀踊、薙刀振りなどが和歌浦を練り歩くもので、東照宮から和歌浦漁港前、片男波を経由してあしべ橋を渡り、再び東照宮へ戻ってきます。途中に設置された5ヶ所のポイントではそれぞれの芸ごとに演舞が披露されるのだそうです。
行列奉行・打鉦に続いて、五色の旗がスタートです。青空に映えてきれいですね。

御輿は近くで見るとものすごい迫力と熱気です。

こちらは「ギャル御輿」。和歌山ご当地アイドルの「ZagaDa」が参加しています。

次は「子ども御輿」。担いでいるのは宝船のようですね。葵のご紋が輝いています。

続いては「御所御輿」。子どもたちが引っ張り、横にはお母さんたちがぴったり寄り添っています。

御輿の後を、東照宮の宮司さんをはじめ神官が馬に乗って続きます。馬の渡御は10年ぶりだそうです。

こちらは「相撲取り」。大人に混じって子どもの相撲取りもいます。かわいいですね。

こちらは「連尺」。行商の反物売りです。

私が滞在したのはここまでです。時間の都合でここで失礼しましたが、まだまだ行列は続きます。
和歌祭の時代絵巻の雰囲気、少しは感じていただけましたでしょうか。私にとっては初体験でしたが、390年間続く和歌山の風物詩を、今後も大事に守っていきたいな、と強く感じました。
(文責:広報課 林 清仁)
Posted by 広報ブログ編集長 at 17:04│Comments(0)
│観光・自然
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。